みなさんこんにちは! 観光情報サイト「旅狼どっとこむ」の旅狼かいとです!
今回ご紹介するのは、福岡が誇る観光地の一つ「太宰府天満宮」です!
日本一の学問の神様「菅原道真」を祀っている神社は連日多くの参拝者や観光客で賑わっており、春には梅の名所としても人気を集めています。受験期に太宰府天満宮へ足を運んだという方や、知り合いの方が太宰府天満宮のお守りを贈ってくれた、なんて方もいるのではないでしょうか!
今回はそんな太宰府天満宮について、見どころやご利益、初夏に見られる紫陽花いっぱいの花手水や夏の天神祭りといったイベントやチェックしたいお土産など、旅行前に知っておきたい情報をお届けします! 太宰府観光を検討している方はぜひ参考にしてみてくださいね!
太宰府の歴史

天満宮についてご紹介する前に、まずは「太宰府」という土地の歴史を簡単にお話します!
筑紫(現在の福岡周辺)はアジア大陸との距離が近く、古くから朝鮮半島との交流の玄関口として機能していました。古墳時代に入ると、日本中に権力を広げたヤマト政権が本格的に整備を進めます。
天智2年(663年)に「白村江の戦い」で日本が唐・新羅の連合軍に敗れると、中大兄皇子(後の天智天皇)は急ピッチで国防政策に着手。大宰府は平城京や平安京と同じ条坊制が布かれ、九州地方の政治や経済を司る役所として、そして、アジア諸国に対する最初の防衛都市として大きな役割を担うようになります。

)、大宰府は平城京や平安京と同じ条坊制が布かれ、九州地方の政治や経済を司る役所として、そして、アジア諸国に対する最初の防衛都市として大きな役割を担うようになります。とは言っても、やはり当時の京都から見れば辺境の都市であることにかわりないのも事実。奈良時代〜平安時代後期における太宰府は貴族の左遷先として利用されることも多かったようです。
また、左遷され晩年を太宰府で過ごした菅原道真は、衛生状態や治安の悪さを嘆いていたとされています。
太宰府天満宮とはどんな神社なの?
それではここから本格的に、「太宰府天満宮」についてご紹介していきます!
太宰府天満宮とは?

太宰府天満宮は「菅原道真(菅公)」を祭神として祀る天満宮の一つです。神様としての道真の名前が「天満大自在天神」であることから、「天神さん」「天神様」の愛称でも知られています。
京都の「北野天満宮」とともに全国約12,000社の天満宮の総本宮とされ、今では「学問の神様」とされる菅原道真の霊廟としても篤く信仰されています。
神紋は、道真が生前愛したと言われる梅を用いた「梅紋」となっています。
菅原道真と太宰府天満宮
では、菅原道真と太宰府天満宮はどのような関係なのでしょうか?
生前の道真

菅原道真は承和12年6月25日(845年8月1日)に生まれたとされていますが、幼少期についての資料はほとんど見つかっておらず、はっきりとしたことはわかっていません。それでも、父や祖父と同じように幼少期からその才能の片鱗を見せていたとは言われており、特に詩歌については、よく口ずさんでは場所に関係なく書きつけてしまうほどだったそうです。
そんな道真は政治分野でも才覚を発揮しており、菅原家は決して高位の家柄ではなかったものの、その能力と地方での功績を買われて宇多天皇に重用されるようになります。そして、朝廷におけるNo.3である右大臣にまで昇進を果たします。

しかし、当時は藤原家が絶対的な権力を握る時代。家格に合わない大出世を続ける道真は、周囲の人々からの中傷も多かったそうです。さらに、それまで道真を重用していた宇多天皇が醍醐天皇に譲位して出家したことで、後ろ盾となっていた宇多天皇(法皇)が京都を留守にすることが多くなっていきます。
その隙を突かれ、道真は「宇多上皇を欺き惑わした」「醍醐天皇を廃して娘婿の斉世親王を皇位 に就けようと謀った」として、太宰府へと左遷されてしまうのでした。
息子たちも流罪となり、太宰府への移動はすべて自費負担、現地では俸給や従者も与えられず、政務にあたることも禁じられた道真。衣食住もままならなかったという説もあり、事実上の死罪と言われています。
道真の祟りと神としての信仰

そんな環境の中で非業の死を遂げた道真。「安楽寺」というお寺に道真が埋葬されると、京都では災害や飢饉が続くようになったのです。
そして、道真左遷の陰謀の中心人物とされている「藤原時平」を筆頭に多くの貴族や皇太子が相次いで死亡し、ついには、会議中だった清涼殿への落雷と火災による凄惨な現場を目の当たりにした醍醐天皇も、心的な体調不良から崩御してしまうのです(「清涼殿落雷事件」)。
これら一連の出来事は道真の祟りであるとされ、道真は京都の北野に「天満大自在天神」として祀られ、太宰府の安楽寺も鎮魂の祈りを込めて整備されることになったのでした。この北野の社が現在の「北野天満宮」であり、安楽寺が「太宰府天満宮」につながっています。

当時は畏怖の念によって祀られていた菅原道真でしたが、次第に怨霊としてのイメージが薄れていき、いつしか生前の生前の秀才ぶりから「学問の神様」として信仰されるようになったとか。
今では日本屈指の学問の神様となっている菅原道真。日本三大怨霊にも数えられる道真ではありますが、この時代を知ってくれれば、少しはうかばれるでしょうかね…!
👉 菅原道真についてさらに詳しく知りたい方はコチラをチェック!
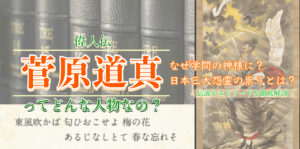
太宰府天満宮のご利益

お次は、気になる太宰府天満宮のご利益をご紹介します!
日本史上初めて、人から神へと至った菅原道真。その道真を祀っている天満宮の総本宮にあたる「太宰府天満宮」は日本屈指のパワースポットですから、ご利益も様々かつ強力なものですよ!
合格祈願・学業上達
「学問の神様」を祀っている太宰府天満宮ですから、まずはなんと言っても「勉強」や「学業」、「合格」についてのご利益ですよね! このご利益を得るために太宰府へ行くという方も多いはず!
また、天満宮における学問の神様は、時代ごとに「書道の神様」「和歌・連歌の神様」「子供の守り神」の要素が加えられてきたのも特徴です!
就職成就:至誠の神様としての天神様

菅原道真(天満大自在天神)は「至誠の神様」というご利益でも知られています。
これは、
才能を評価され、天皇の厚い信頼を受けても奢ることなく誠心誠意日本の発展のため尽くし、左遷された後も皇室と日本の安泰、また自身の潔白を最後まで神々に祈っていた
という「生涯を一貫して誠を尽くしていた菅原道真の清らかな生き方」から生まれたご利益とされています。
この性質と学業成就・合格祈願のご利益が合わさり、太宰府天満宮は「就職成就」のご利益でも知られていますね!
厄除け

最後は神社によくある「厄除け」のご利益です!
太宰府天満宮に祀られている菅原道真は「日本三大怨霊」にも数えられる大怨霊でもあります。実は天満宮の最初の役割は「祟り封じ」だったと言われており、これが「厄除け」の役割を担っていたのです。
日本三大怨霊である菅原道真を祀る太宰府天満宮は、さぞ強力な厄除けの加護を持っていることでしょう…! まさに、「毒をもって毒を制す」というわけですね!
太宰府天満宮の見どころ
それでは! 太宰府天満宮に行ったら絶対にハズせない見どころを駅側から順番にご紹介していきます!
表参道

最寄り駅の太宰府駅からすぐにある鳥居をくぐると、早速参道を歩くことができます。そしてこの参道には、古くから太宰府天満宮への参拝者をもてなす茶屋が並んでいます。
最近では、福岡の名産である明太子や太宰府の名物である梅を使った食事処・甘味処も多く並んでおり、太宰府の雰囲気に合わせた”和”の内装が話題となったスターバックスも軒を連ねていますね!
他にも、「太宰府バーガー」でお馴染みの「筑紫庵本店」やもなか専門店「太宰府参道天山福岡」など、福岡を代表するグルメの食べ歩きができちゃいますよ!
御神牛

「道真の遺骸を運んでいた牛が安楽寺の前で伏した」という逸話から生まれたのが、「御神牛」と呼ばれる牛の像。
撫でると道真の知恵を授かることができるということで、日本各地の天満宮にも置かれています。太宰府に足を運んだらぜひこの牛の頭をなでなでしましょう!
心字池と太鼓橋

境内に入ると最初に出迎えてくれるのは、大きな池と池に架かる3本の太鼓橋です。
この池は上から見ると「心」という漢字の形に見えることから「心字池(しんじいけ)」と呼ばれており、本殿へと続く3本の橋はそれぞれ「過去」「現在」「未来」を表しているとされます。
これらの橋を渡ることで心と身体を清め、天神様こと道真の前へ向かうという習わしだそうですよ!
楼門

本殿への入り口にあたるのが「楼門」です。
太宰府天満宮の楼門は表と裏で形状が異なっている珍しいつくりになっているのが特徴で、心字池側から見ると屋根が二段になっているのに対し、本殿側から見ると最上段の屋根のみに見えるのです!

本殿

学問の神様としての信仰を集める太宰府天満宮の中心地が、「天満大自在天神」こと「菅原道真」を祀る「本殿」ですね!
本殿の見どころとしては、向かって右側にある「飛梅」と向かって左側にある「皇后の梅」に触れておくべきでしょう!
飛梅

ことあるごとに和歌を口ずさんでいたという道真は中でも梅がお気に入りの植物だったようで、京都の自宅の庭にも梅を植えていました。
そして太宰府に左遷されたある日、道真が自分の家にあった白梅を想い、
東風(こち)吹かば にほひおこせよ梅の花 あるじなしとて春な忘れそ
という和歌を詠んだところ、なんと京都から一晩で太宰府の道真の住む屋敷まで梅の木が飛んできたというのです。
その白梅こそが本殿の前に植えられた「飛梅」であり、このお話は「飛梅伝説」として知られています。

ちなみにこの歌は
春風が吹いたら、香りをその風に託して大宰府まで送り届けてくれ、梅の花よ。
主人である私がいないからといって、春を忘れてはならないぞ。
という意味だそうですよ!
皇后の梅

飛梅と合わせて見ておきたいのが、対となるように植えられている「皇后の梅」です。
大正天皇の皇后「貞明皇后」が1922年(大正11年)に自ら手植えされたという梅の木で、白い飛梅と異なりかわいらしい紅色の梅になっていますよ!
厄晴れひょうたん掛所

こちらは本殿の裏側にある「厄晴れひょうたん掛所」という場所です。
実は太宰府では、ひょうたんも名物の一つとなっているのです! というのも、太宰府に道真が祀られてからというもの、「天神様がこよなく愛した梅の木の下で”ひょうたん酒”を飲むと厄から逃れられる」という信仰が生まれたというのです。
かわいらしいフォルムのひょうたんがずらっと並んでいる風景は、そうお目見えできるのものではありません。まさに、穴場なインスタ映えスポットと言えますね!
大樟

本殿に向かって左側、皇后の梅側の門をくぐると立っているのが「大樟(おおくす)」です。
太宰府天満宮の境内には約80本のクスノキがあり、うち51本が県指定天然記念物に指定、さらに2本は樹齢1,000年を超えるとも言われており、国指定天然記念物に指定されているのです。
写真のクスノキは国指定の天然記念物の一本。太宰府天満宮のひそかなパワースポットというわけですね!
ちなみに、境内には”裏山”のような場所もあり、こちらも太宰府の手付かずの自然を満喫する上ではちょっとした見どころになっているように感じました。時間がある方はぜひ寄ってみてください!

👉 太宰府天満宮と同じく菅原道真を祀るパワースポット! 北野天満宮について詳しくはコチラ

梅の名所としての太宰府天満宮

春の太宰府天満宮は、道真が愛した梅の名所としても知られています。
本殿に植えられている飛梅や皇后の梅のほかにも、太宰府天満宮にはいたるところに奉納された梅の木が植えられており、その数は200種・6,000本にも及ぶと言われているのです!
太宰府天満宮の梅の花の見頃は例年2~3月。道真の命日が現在の暦の2月25日とされていることもあり、この時期は催し物も多く開かれています。この時期に福岡や太宰府を観光する方はぜひチェックしてみてください!
梅ヶ枝餅

梅の花といえば、太宰府名物「梅ヶ枝餅」も忘れてはいけません!
名前に「梅」とありますが、スタンダードな「梅ヶ枝餅」は梅の風味がするわけではなく、餅の中に普通のあんこが入ったシンプルなものになっています。
その由来には、「道真が大宰府へと左遷され心身ともに憔悴していた折、老婆が道真に餅をふるまい、その餅が道真の好物になった」という逸話や「道真が左遷直後の食事もままならない軟禁状態下におかれていた際、老婆が梅の枝の先に餅を刺して格子ごしに差し入れた」という逸話が関係していると言われています。
こういう時は決まって「優しい老婆」が登場するのが、日本の昔話や逸話のお約束な感じがしますね!笑

ちなみに、、太宰府天満宮の絵馬は梅の模様が描かれているのが特徴です!
梅の時期に己を試す挑戦をし、桜舞い散る季節に別れと出会いを繰り返す。やはり日本の四季は美しいですね~!
太宰府天満宮 主な季節の催し物・イベント
梅以外にも、太宰府天満宮では季節のイベントが目白押しです! ここではその中でも大きなものを取り上げていきます。
季節ごとに色が変わるおみくじ

太宰府天満宮のおみくじは季節ごとに色が変わるのが特徴で、その風景は「新日本様式」100選にも選ばれています。
ラグビーワールドカップが開催された2021年には日本代表のイメージカラーも使用されており、その年に応じて様々楽しめるのもポイント!
足を運ぶたびにおみくじに注目してみると、新しい発見があるかもしれませんよ!
節分厄除祈願大祭

節分の日に合わせて毎年行われる祭典が「節分厄除祈願大祭」です!
期間中に厄除祈願を受けると、御神木「飛梅」の下でひょうたん酒を授かることができます。「梅の木の下でひょうたん酒を飲むと難を免れることができる」という伝承にあやかったイベントというわけですね!
節分当日には「豆まき神事」も行われますよ!
令和4年(2022年)の開催日
・1月25日(土)~2月3日(月)
・豆まき神事:2月3日(月)の10:30頃と14:00頃
曲水の宴

「曲水の宴」は、平安時代の宮中行事を再現した禊祓の神事です。京都のお祭りでは見られる光景ですが、福岡では滅多にお目にかかることができない珍しい行事です。
観光の時期が合ったらチェックしておきたいイベントですね!
開催日
毎年3月の第一日曜日
観覧について
・入場開始は11:00、宴は12:00~15:00で開催予定
・観覧席は約1,100席用意されており全席自由席
七夕揮毫大会

「七夕揮毫大会」は、祭神である菅原道真が「書の三聖」の一人に数えられることから書道上達の成果を伝えるものとして始まった催し物。
幼稚園児〜高校3年生までが課題を提出し、受賞作品を選出するイベントとなっています。
令和4年(2022年)の開催日
8月1日~3日
【申し込み締め切り】
・席上揮毫:7月5日(火)
・郵送揮毫:6月25日(土)必着、作品の提出は7月22日(金)必着
【参加料】
一人500円
夏の天神まつり

毎年の7月24日・25日に、祭神である菅原道真(天神様)の誕生日をお祝いするとともに、人々が病気や事故に遭うことなくこの夏を無事に過ごせるよう「夏越祓え」の神事が行われます。
25日の夜に天神様の御霊を偲んで行われる「千灯明(せんとうみょう)」は、太宰府の夏の夜を彩る風物詩としても知られていますよ!
開催日
毎年7月24日・25日
※24日は夏越祭、25日は誕生祭として斎行される
特別受験合格祈願大祭

毎年10月に催されるのが「特別受験合格祈願大祭」です。10月18日には「特別受験合格祈願大祭」当日祭斎行が行われます。
期間中は登龍門の伝説にならい「飛龍天神ねぶた」が楼門に掲げられ、受験合格祈願を受けた方には期間限定のお札・お守り・絵馬・掛け襟が授与されます。
受験生は息抜きも兼ねて、この時期に太宰府天満宮に足を運んでみてはいかがでしょうか!
開催日
毎年10月1日~31日
夏祭り「茅の輪神事」(宝満宮 竈門神社)

毎年7月下旬に、太宰府天満宮から2kmほど北東へ向かったところにある「宝満宮 竈門神社」で行われるのが「茅の輪神事」と呼ばれる夏祭りです。
地元氏子さんたちの手で奉製された「茅の輪」を左回り、右回り、左回りと8の字を描くように3回くぐると、幸運がもたらされると言われていますよ!
令和4年(2022年)の開催日
7月23日(土) 11:00〜
宝満宮 竈門神社にもぜひ寄ってみてください!

ちなみに、竈門神社は九州でも屈指の縁結びのパワースポットと言われており、特に紅葉が美しい自然豊かな境内と山登りをすることでたどり着ける奥宮への参拝が密かな人気を集めている名所です!
『鬼滅の刃』がブームとなってからは、主人公の竈門炭治郎と同じ名前であることから一気に知名度がアップしたことでも知られていますね!
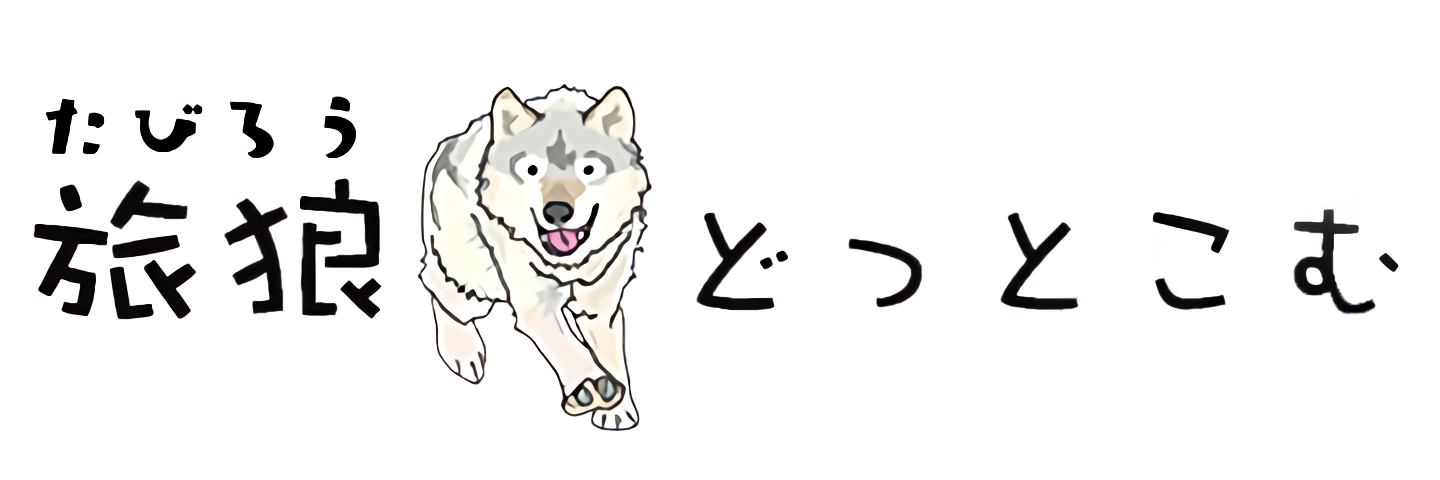


この記事へのコメントはこちらから!
コメント一覧 (2件)
[…] 「北野天満宮」は、福岡県太宰府市の「太宰府天満宮」とともに”学問の神様”こと「菅原道真」を祀る全国天満宮の総本社として、天神信仰の中心的役割を担っています。 […]
[…] 今では、福岡県太宰府市の「太宰府天満宮」とともに、学問の神様「菅原道真」を祀る全国天満宮の総本社として天神信仰の中心的役割を担っている北野天満宮。 […]