みなさんこんにちは! 世界・日本の観光地や旅行情報、歴史や雑学をご紹介している旅狼かいとです。
今回ご紹介する京都の紅葉の名所は、その名の通り「金閣寺」「北野天満宮」周辺の「金閣寺エリア」です!
金閣寺一帯のお寺は、紅葉の名所というよりは各お寺ならではの特徴が強く、非常に深い歴史を持っているのが特徴です。そのため他のエリアに比べて、紅葉の時期のみならず一年中楽しむことができるのが最大の魅力ですね!
その中でもとりわけ人気を誇る、「北野天満宮」「龍安寺」「仁和寺」「退蔵院」、そして「金閣寺」について、見どころや歴史、拝観料など、旅行前に知っておきたい観光情報をお届けしていきます!
北野天満宮

「北野天満宮」は、福岡県太宰府市の「太宰府天満宮」とともに”学問の神様”こと「菅原道真」を祀る全国天満宮の総本社として、天神信仰の中心的役割を担っています。
藤原時平の政略によって太宰府へと左遷され、そのまま没した菅原道真。道真の死後、朝廷では落雷などの自然災害が頻繁に起こるようになり、加えて藤原時平をはじめとする道真失脚の陰謀に関わったとされた人物が、次々と死んでしまうという出来事が起こります。人々はこれを「道真の祟り」だと信じ、朝廷は道真の左遷を撤回して官位を復し、最終的には太政大臣の位まで贈ります。さらには太宰府の地と京都の北野の地に、道真を祀る社殿を造営しました。

梅の名所として長く知られてきた北野天満宮でしたが、近年は秋の見どころ「もみじ苑」もとても人気! 境内に一部残る、豊臣秀吉が京都を囲むよう作らせた土塁「御土居」が史跡となっている場所で、そこに植えられたもみじが紅葉スポットとなっているのです。
加えてこのもみじ苑は、春の時期には瑞々しく清々しい青もみじの名所としても人気を集めており、一年を通じて日本の自然を楽しむことができる観光地なのです!
今回の写真は紅葉の色づき始めという感じで、青もみじとほんのり色付いたもみじの絶妙なコントラストが素晴らしかったです!
北野天満宮の拝観情報・ライトアップ・紅葉の見頃・アクセスなど

拝観時間
【開門時間】
7:00~17:00
・社務所・授与所:9:00~17:00
・御祈祷:9:00~16:00
【縁日】
毎月25日の6:30~21:00
境内の拝観料
自由散策のため無料
史跡 御土居もみじ苑の特別公開(2024年)
【開催期間】
2024年秋は、10月25日(金) ~ 12月8日(日)
【拝観時間】
9:00~16:00(最終受付は15:40)
【御土居のもみじ苑の拝観料(茶菓子付き)】
・大人:1,200円
・小人:600円
2024年のライトアップ(夜間特別拝観)
【ライトアップ開催期間と時間】
2024年秋は、11月9日(土) ~ 12月8日(日)
【ライトアップ開催時間】
日没~20:00(最終受付は19:40)
※ライトアップ期間中、社務所・授与所は9:00~19:30となる。
【ライトアップ拝観料(茶菓子付き)】
・大人:1,200円
・小人:600円
※昼夜入れ替えなし。日中の拝観券と共通。
紅葉の見頃

・色づき始め:11月上旬
・見頃:11月中旬~12月上旬
秋以外の特別拝観
【梅苑公開】
例年2月初旬~3月下旬まで
【史跡 御土居の青もみじ苑】
例年5月上旬~下旬
観光のおすすめ時間
毎月25日は縁日が開催されるため、普段より混雑するので注意
アクセス・駐車場

〒602-8386
京都市上京区馬喰町 北野天満宮社務所
TEL:075-461-0005
・京福電車「白梅町駅」から徒歩5分
・市バス10・50・51・55・101・102・203系統で「北野天満宮前」で下車後すぐ
【駐車場】
・9:00~17:00
・300台完備(毎月25日は縁日のため駐車不可)

龍安寺

「石庭」が見どころとして知られる「龍安寺」。
龍安寺は、室町幕府の管領にして守護大名であり、応仁の乱の際には東軍の総帥でもあった細川勝元が、宝徳2年(1450年)に創建した禅寺になります。京都を焼け野原と化した「応仁の乱」によって一度は焼失してしまいますが、勝元の子の細川政元と4代目住職の特芳禅傑によって再興されています。
江戸時代中期に刊行された絵入りの名所案内書『都名所図会』(現代で言うガイドブック)では、龍安寺の「鏡容池」はオシドリの名所として紹介されています。
当初は、今日における龍安寺の”代名詞”である石庭よりも、池を中心とした池泉回遊式庭園の方が有名だったそう。そして、龍安寺の紅葉の名所として今日紹介されるのも、この鏡容池なのですよ!
境内の南側半分を占める池泉回遊式庭園は、紅葉の時期以外でも四季折々の自然を楽しむことができますよ!
龍安寺の石庭について

紅葉の名所としては、「鏡容池」を中心とした池泉回遊式庭園が最大の見どころですが、やはり龍安寺に来たからには石庭は見逃せない…! ということで、石庭についてここでちょっぴり触れておきましょう!
上述のように、もともとは庭園によって人気を集めていた龍安寺が、石庭によって一気に注目を集めることとなった理由。
それは、昭和50年(1975年)にイギリスの女王エリザベス2世が日本を公式訪問した際、エリザベス2世が龍安寺の石庭を絶賛したことで世界中で日本の禅(ZEN)がブームとなって広がったからなのです! エリザベス2世が日本の”侘び寂び”を感じ、発信してくれて本当によかった。。

ここで、そんな石庭の人気の秘訣である「石庭の解釈」もせっかくですのでご紹介!
大小15個の石が配置された石庭は、見方や各人によって解釈が変わるのが特徴で、代表的なものは2つ。
1つ目は、「虎の子渡しの庭」と呼ばれる、親虎が子虎を連れて川を渡るという中国の諸話に基づくもの。
2つ目は、石の配置を7・5・3の組み合わせでまとめて見る「七五三の庭」と呼ばれる解釈。
古くから奇数はめでたい数字とされており、縁起の良い数での配石と捉えるものになります。

さらにこの2つに加え、石庭をどこから眺めても同時に見える石は14個という仕掛けもあるのですよ!
これは、「15」という数字が「完全」を意味することから、「人間が完全なものになることはない」ということを表しているとも、「完全な人間になれるよう(15個目の石が見えるようになるよう)努力せよ」ということを表しているとも言われています。
このような庭を使った遊びは多くの庭園に見られますが、この龍安寺の石庭はその中でも随一という訳!
これらの解釈をなぞってみるのもよし、自分で新たな解釈を見出してみるのもよし、何も考えず、ただ静かに石と砂の庭と対面し、心を澄ますのもよし。日本の侘び寂びが詰まった、実に素晴らしい寺院ですね〜!
龍安寺の拝観情報・ライトアップ・紅葉の見頃・アクセスなど

拝観時間
【3月1日~11月30日】
8:00~17:00
【12月1日~2月末日】
8:30~4:30
拝観料
・大人:600円
・高校生:500円
・小中学生:300円
紅葉の見頃

・色づき始め:11月中旬
・見頃:11月下旬~12月上旬
観光のおすすめ時間
開館直後
アクセス・駐車場
〒616-8001
京都府京都市右京区龍安寺御陵ノ下町13
・嵐電(京福電鉄)「龍安寺駅」から徒歩7分
・市バス「龍安寺前」からすぐ
・市バス「立命館大学前」から徒歩7分
【駐車場】
100台分(石庭拝観者に限り1時間無料)
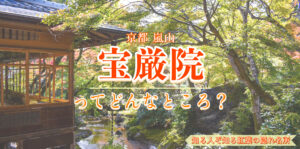
仁和寺

金閣寺エリア最大の観光地と言っても過言ではないのが、ここ「仁和寺」です!(読み方は「にんなじ」です!)
日本で初めて「法皇」の称号を用いた宇多天皇が初代門跡(皇族・公家が住職を務める特定の寺院の住職のこと)として創建した仁和寺。宇多法皇が仁和寺伽藍の西南に「御室(おむろ)」と呼ばれる僧坊を建てて住んだことから、「御室御所」とも呼ばれていました。以降明治維新まで、宇多法皇を継ぐ形で仁和寺の門跡は代々皇室出身者が務めるようになり、皇族や貴族の保護を受け、大きな力を持った寺院としてありました。
応仁の乱の際には伽藍が全焼してしまいしばらくは荒廃したままとなっていましたが、江戸時代・徳川家光の時代になってようやく再建されます。この際、皇居(現在の京都御所)の建て替えと時期が重なったため、皇居の紫宸殿や清涼殿、常御殿などが仁和寺に下賜され、境内に移築されました。
その後も何度か衰退と再興を繰り返しますが、昭和時代に入ると真言宗御室派の総本山となり、近年では平成6年(1994年)に「古都京都の文化財」としてユネスコの世界文化遺産に登録されました。

観光地としては、南禅寺三門と知恩院三門とともに「京の三大門」の一つに数えられる正門「二王門」や、現存する最古の紫宸殿である国宝「金堂」、御所を思わせるほどの雅さを誇る「御殿」、御殿内の白川砂を敷き詰めた南庭と自然と石のコントラストが美しい池泉式の北庭など、王朝風の広大な境内には多くの見どころが満載です!
さらに仁和寺は、桜と紅葉の名所としても知られています。特に「御室桜」と呼ばれる遅咲きの桜は、日本全国の規模で見渡しても非常に名高い名所として人気を集めています。
仁和寺の拝観情報・ライトアップ・紅葉の見頃・アクセスなど

拝観時間
【3月〜11月】
9:00~17:00(御所庭園の受付終了は16:30)
【12月~2月】
9:00~16:30(御所庭園の受付終了は16:00)
拝観料
※すべての拝観料において、高校生以下は無料
境内自由(御室桜開花期は境内見学でも500円必要:紅葉期間中は関係ありません)
【御所庭園】
800円
【霊宝館 秋季名宝展】
500円
その他、御殿、観音堂、霊宝館の拝観がそれぞれセットになった共通券も販売
紅葉雲海ライトアップ(2024年の夜間特別拝観)
【開催期間】
2024年秋は、10月25日(金) 〜12月8日(日)の金土日月祝日のみ開催
※11/1, 11/2, 11/15, 11/30, 12/1 は開催しない。
【拝観時間】
18:30~21:00
(受付開始は18:00、受付終了は20:30)
【拝観料】
2,800円(高校生以下は無料)

霊宝館 秋季名宝展
【開催時期】
2024年秋は、10月1日(火) 〜12月1日(日)
【休館日】
・毎週月曜日
※10/14, 11/4は開館
【拝観時間】
10:00~16:30(受付終了は16:00)
紅葉の見頃

・色づき始め:11月上旬
・見頃:11月下旬
桜の見頃
4月上旬~4月中旬
観光のおすすめ時間
午前中
アクセス・駐車場
〒616-8092
京都市右京区御室大内33
・嵐電(京福電鉄)「御室仁和寺駅」から徒歩3分
・市バス「御室仁和寺」からすぐ
【駐車場】
100台分(9:00~17:30、駐車料金は500円)
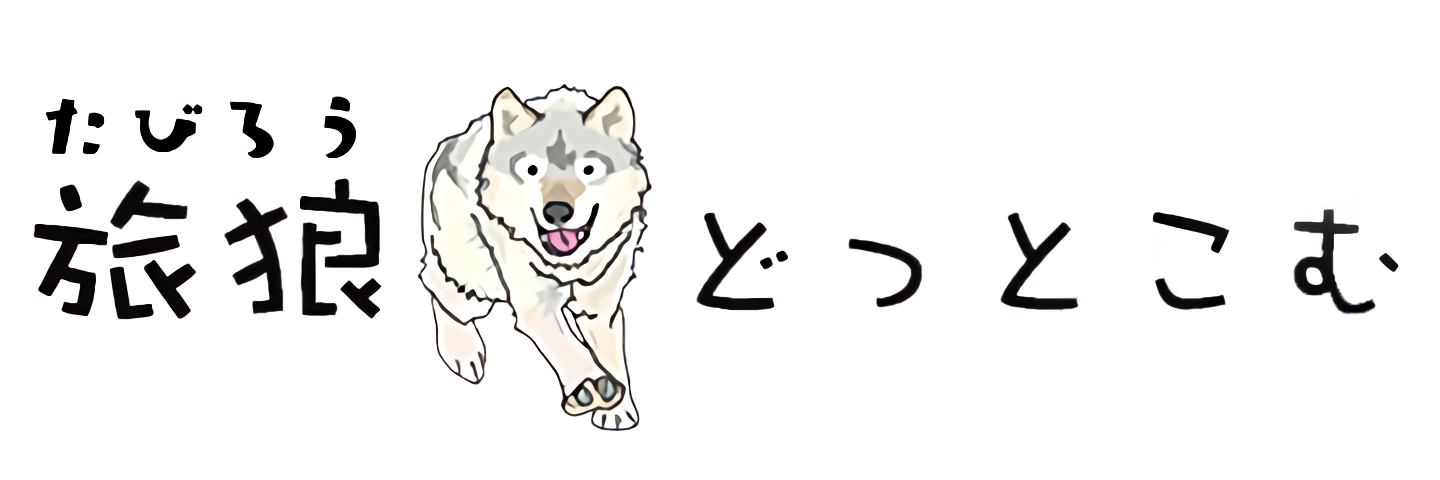

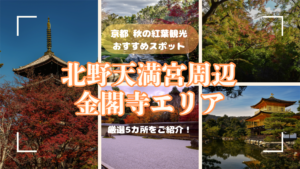
この記事へのコメントはこちらから!
コメント一覧 (1件)
[…] 👉 金閣寺周辺の紅葉の見どころを詳しくみてみる […]