みなさんこんにちは!観光情報サイト「旅狼どっとこむ」の旅狼かいとです!
突然ですが、あなたは「かちかち山」って聞いたことありますか? 小学校の国語で聞いたことがある…かもしれないお話だと思います。
今回のブログでは、山梨県の富士山麓にある富士五湖の一つ「河口湖」の湖畔に立つ「かちかち山」こと「天上山」についてと、そこにある「〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ」の観光案内をしていきます!
加えて、このかちかち山が登場する民話『かちかち山』のお話もご紹介していきます。絵本や歌によって現在にまで残る物語は、それぞれに教訓やメッセージ性が存在するからこそ残っているもの。加えて『かちかち山』は、かの「太宰治」も物語として描いているのです!
家族旅行や友達との旅行、カップルの旅行にピッタリな河口湖の観光前に知れば、さらに旅行が楽しくなること間違いなし! カチカチ山ロープウェイについてぜひ参考にしてみてください!
目次
かちかち山(天上山)の基本情報

まずは「かちかち山」の基本情報をご紹介します。
「かちかち山」は正式な名称ではなく、山自体は「天上山」という名前です。では、どうして「かちかち山」と呼ばれるようになったのでしょうか?
それは、太宰治が描いた物語『カチカチ山』で、この天上山が「カチカチ山」として舞台設定されたからなのです!
太宰治といえば、『走れメロス』や『人間失格』などの作品で有名な日本を代表する作家ですね! 太宰治の『カチカチ山』は『御伽草子』という短編集に収録されている物語で、太宰治が童話『カチカチ山』を自身の解釈によって物語調に書いていくというものになっています。
つまり、元々の民話『かちかち山』では舞台がここ天上山であるという記載はなく、太宰治が「ここがカチカチ山だ」と物語の舞台にしたからいつの間にかここ天上山が「かちかち山」になったというわけなのです! 太宰治の影響力、さすがは日本を代表する文豪ですね…!
『かちかち山』の絵本や原作、太宰治の物語について、詳しくは記事の後半でご紹介しています!
〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイの見どころ
ではここから本格的に、かちかち山のロープウェイを観光したらチェックした見どころをご紹介していきます!
ゴンドラ

ロープウェイといえば、やはりゴンドラからの風景が見どころとなりますね!
かちかち山の山頂からの風景は、どちらかといえば富士山の展望が中心です。河口湖は見えるのですが、遮蔽物があって完全なパノラマとはなっていません。対してゴンドラからの眺めであれば河口湖が一望できるので、ぜひカメラを構えてご乗車ください!
 乗り場でチケットを買って入場すると、早速かちかち山の物語でお馴染みのタヌキが出迎えてくれます!
乗り場でチケットを買って入場すると、早速かちかち山の物語でお馴染みのタヌキが出迎えてくれます!ちなみにゴンドラの乗車チケットは、一般的な「往復券」はもちろんのこと、「片道」や遊覧船との割引セット券など、数多くの種類が用意されています。約40分のハイキングコースを使えば徒歩でも天上山を登ること・降りることもできるので、プランに沿ったチケットを購入してみてください!
ロープウェイのゴンドラからは、、
このように河口湖が一望できます!
上りの際は進行方向向かって左側に河口湖が見えるので、左側に陣取ると景色をより楽しめますよ!
たぬき茶屋
山頂に着くと一軒の建物が建っています。こちらが「たぬき茶屋」と名付けられた休憩所です!
たぬき茶屋では、お土産を購入できたり焼きたてのお団子がいただけたりします。「茶屋でお団子をいただく♪」という粋なことができるなんて、ちょっと嬉しいですよね!
 和菓子大好き勢は食べずにはいられない!
和菓子大好き勢は食べずにはいられない!茶屋の前でもウサギがタヌキをいじめてましたが、ここでもウサギがタヌキを、、笑

このように、民話のワンシーンを実際に像にしているものが頂上には結構あるのですが、、こうして見るとタヌキがアホっぽく見えてしまいますし、何よりウサギもなかなかにヒドいですよね。。笑
たぬき茶屋の展望台

ロープウェイ頂上の展望台は、上述のたぬき茶屋の屋上に設置されています。展望台からは、河口湖とは反対の富士山側の風景を楽しむことができますよ!
写真の手前に街があり、奥に広がる緑の森が「青木ヶ原樹海」です。そしてその先に富士山が裾野を広げて聳えています!
天気によってだいぶ印象が変わる景観となりますが、河口湖をはじめとする富士五湖に旅行したらぜひ見ておきたい絶景なのは間違いありませんね!
カチカチ山絶景ブランコ
 画像出典:〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ 公式サイト
画像出典:〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ 公式サイト
2021年11月にできた新名所が、「カチカチ山絶景ブランコ」です!
気分はまさにアルプスの少女! 展望台からさらに高い見晴らし台にある大きなブランコをこげば、今まで経験したことがない富士山の絶景を楽しめること間違いなしです!
ブランコ利用について
【利用可能時間】
平日:10:00~14:00
土日祝日:10:00~11:30、13:00~16:00
※悪天候・点検等により利用できない場合あり
【料金】
1人500円
【利用制限】
身長110センチ以上、体重100キロ未満
絶景やぐら
 画像出典:〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ 公式サイト
画像出典:〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ 公式サイト
標高1110mの崖から迫り出す一本橋のようになっているのが、「絶景やぐら」です!
やぐらという名前の通り空中に浮いているかのような見晴らし台となっており、何も遮るものがない場所から雄大な富士山を堪能することができますよ!
天上の鐘
 画像出典:〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ 公式サイト
画像出典:〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ 公式サイト
こちらは「天上の鐘」です! 見るからにカップル向けな感じがありますが、それ以外の方にもありがたいパワースポットなのですよ!
富士山は「霊峰富士」とも呼ばれ、古くから神聖なものとして讃えられてきました。そんな富士山を眺めながら鐘の音を響かせれば、願いが叶うこと間違いなし!
ということで、この天上の鐘を鳴らすことで無病息災のご利益をいただけるそうですよ!
またこの形からもわかる通り、恋愛成就のご利益もあるとか…!
というのも、この「天井の鐘」は鐘の鳴らし方によっていただけるご利益が変わるのです。近くに鐘の音の鳴らし方は書いてあるので、いただきたいご利益の方法で鐘を鳴らしてくださいね!
うさぎ神社
 画像出典:〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ 公式サイト
画像出典:〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ 公式サイト
続いては「うさぎ神社」です!
この神社はウサギを御神体として祀っている珍しい神社で、両脇には狛犬ならぬ”狛兎”が鎮座しています。
向かって左の後ろ足で立っているウサギが「富士見兎」、向かって右の頭を伏せているウサギが「夢見兎」という名前。「富士見兎」の脚に触れることで「健脚」のご利益、「夢見兎」の頭を撫でると「知恵授受」のご利益をそれぞれいただくことができます! 特に「健脚」については、この山頂から繋がっている三ツ峠を歩く方々の安全祈願と健脚も祈ってくれているみたいですね!

「三ツ峠」は、日本二百名山、山梨百名山、日本の新・花の百名山といった数々の「百名山」に選ばれており、「花の山」として親しまれています。
日本ウォーキング協会のコースにも認定されており、気軽に登山を楽しみながら富士山の眺めやたくさんの植物と触れ合うことができる名峰なのです! 時間に余裕がある計画の方は、ぜひ河口湖でのアクティビティとして三ツ峠ハイキングにも挑戦してみてください!
かわらけ投げ
 画像出典:〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ 公式サイト
画像出典:〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ 公式サイト
見どころの最後は「かわらけ投げ」です!
かわらけ投げの元々の始まりは、厄除けなどの願掛けのために高所から素焼きの器や酒器を投げていたという風習だとされています。それがいつの間にか「高所から素焼きの器を投げる」という形だけを残して、花見などでの余興となったり山での願掛け行為の一つとなっているのです。
実は「かわらけ投げ」そのものは日本各地のロープウェイやご利益がある山々に備え付けられているのですが、ここカチカチ山こと天上山のかわらけ投げは「投げたお皿が的に当たれば恋の願いが叶う」と言われているのです!
というのも、天上山には古くより「縁結びの女神」であり姉の「磐長姫(いわながひめ)」と「美の女神」であり妹の「木花開耶姫(このはなのさくやびめ)」という姉妹の二女神が祀られているからなのです。
ゲーム感覚でも楽しめるかわらけ投げ、ぜひみなさんで挑戦してみてください!
神話『磐長姫と木花開耶姫』
上述の「磐長姫(いわながひめ)」と「木花開耶姫(このはなのさくやびめ)」は、『古事記』や『日本書紀』では非常に重要な役割を果たす女神さまとなっています。面白いお話なので、ここで少し紹介しますね!
(かちかち山やロープウェイの紹介とは関係ないため、興味がない方は読み飛ばしてください!)
姉妹の女神である磐長姫と木花開耶姫は、仲睦まじく暮らしていました。美の女神たる妹の木花開耶姫は絶世の美女だったのに対し、縁結びの女神たる姉の磐長姫の見た目はとても酷かったと言います。
そんな女神たちが暮らしていたある日、妹の木花開耶姫は天照大神の孫である「邇邇芸命(ににぎのみこと)」に求婚されます。邇邇芸命は地上を統べるために天から遣わせれた神様であり、天照大神といえば日本神話における主神の女神です。そんな女神さまの孫からの求婚ですから、姉妹の父である「大山津見神(おおやまつみ)」は大変に喜び、求婚された妹の木花開耶姫のみならず姉の磐長姫も共に差し出します。
この際、姉妹の父大山津見神は
「姉の磐長姫を妻にすれば、子々孫々命が岩のように永遠となり、妹の木花開耶姫を妻とすれば、子々孫々木や花のように華やかに繁栄するだろう」
という誓約を邇邇芸命にたてます。
しかし邇邇芸命は、絶世の美女と謳われた木花開耶姫のみをめとり、見た目が醜い磐長姫は大山津見神のもとに返してしまいます。
邇邇芸命のこの行為に大山津見神は激怒し、
「磐長姫を返してきたことで、子孫は短命になるだろう」
と告げたのです。
この出来事がきっかけとなり、「今の人間の命は神さまたちから比べれば非常に短命なものとなった」とされているのです。
(『日本書紀』では「邇邇芸命との間の子を身ごもった木花開耶姫を姉の磐長姫が呪い、これによってその後の命、つまり今の人間が短命になった」という流れになっています。)
人間の寿命が今の長さになったきっかけの出来事に関わっている女神ですから、実は日本神話でもとても有名なエピソードで、かつ有名な神々なのですよ!
ちなみに、絶世の美女である木花開耶姫が「美の女神」なのはなんとなく想像がつきますが、磐長姫が「縁結びの女神」かどうかというのは、冷静に考えるとよくわからないですよね。
磐長姫が「縁結びの女神」だと考えられるようになったのは、
「磐長姫」は「石長比売」とも書かれる
↓
「石長」
↓
「石(岩)のように長い」
↓
「岩のように永遠」
↓
「永遠に変わることのない女」
↓
「永遠に心変わりすることがない女」
↓
恋愛・縁結びの女神!
という解釈からだそうですよ!
ただ日本書紀では、経緯はどうあれ妹を呪っていますからね。呪っておきながら「心変わりすることがない女」なんて、ちょっとゾッとする話ですよね。。笑
実際、日本書紀のエピソードから、磐長姫は「縁切りの女神」としてのご利益もあると言われています。日本各地の縁結びのパワースポットにも、実は縁切りのご祈祷やお祓いがあったりするので、縁結びと縁切りは表裏一体ということなのですね…!
あわせて読みたい
【京都】すごいスピリチュアルスポットと話題!貴船神社の見どころ・ご利益・ライトアップ・駐車場情報など
今回は京都屈指の観光名所「貴船神社」をご紹介!縁結びのご利益や水占い、龍穴や水の神様の伝説が残る奥宮は大人気のパワースポット!縁切りや呪いの藁人形、丑の刻参りにも関わる歴史や見どころ、夜のライトアップ情報や所要時間、アクセスや行き方をお届けです!
河口湖・富士山パノラマロープウェイの観光地情報
ロープウェイの紹介の最後に、料金や営業時間、アクセス等の基本情報をご案内します。
営業時間
平日:9:30〜16:00(下りの最終は16:20)
土日祝日:9:30〜17:00(下りの最終は17:20)
ロープウェイの料金
【往復】
大人(中学生以上):900円
小人(小学生):450円
【片道】
大人:500円
小人:250円
※往復・片道ともに小学生未満は大人1名につき1名まで無料
【ペット(犬等)】
小型:200円
中型:400円
大型:乗車不可
※ゴンドラ内ではペット用ハードケースに入っていることが条件
アクセス

富士山パノラマロープウェイへのアクセスは、河口湖へ行くのとほぼ同じ道順となります。
高速バス・電車を利用する場合
①JR中央線の富士急行線「河口湖駅」へ
②周遊バス(約3分)か徒歩(約15分)でロープウェイのゴンドラ乗り場へ
自家用車の場合
【中央自動車道を利用する】
・関東方面から:大月JCTを経由して河口湖ICから約15分
・関西・中部方面から:一宮・御坂ICから国道137号線を利用して約40分
【東名高速道路を利用する】
・御殿場ICから国道138号線(須走道路)・須走ICを経由して東富士五湖道路の「富士吉田IC」から約10分
【駐車場】
「〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ」の専用駐車場か、道路を挟んで向かいにある河口湖畔の県営無料駐車場を利用する


















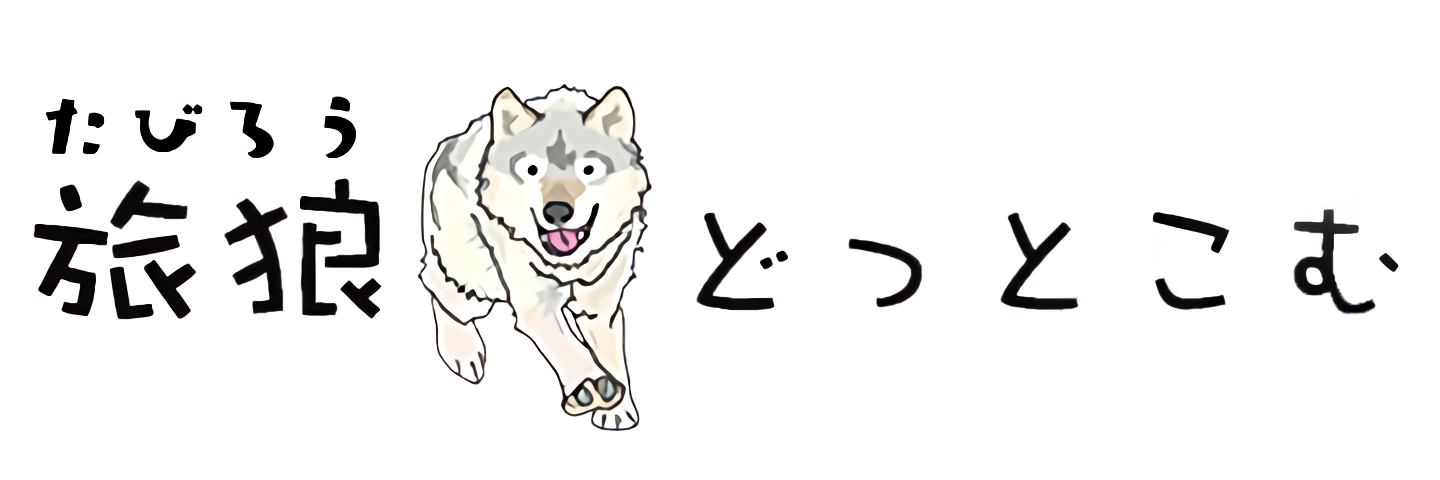

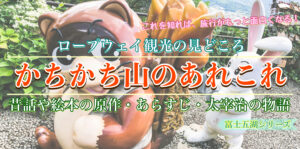
この記事へのコメントはこちらから!
コメント一覧 (1件)
[…] なみに、人の寿命が現在の長さになったことにも、磐長姫・木花開耶姫と邇邇芸命の物語が関わっているのですよ! 詳しく知りたい方はこちらの「かちかち山」の記事をご覧ください! […]