みなさんこんにちは!観光情報サイト「旅狼どっとこむ」の旅狼かいとです!
今回は、京都屈指の観光地である「祇園」とその周辺の「八坂」「二寧坂」「清水」エリアを観光した際の旅日記をお届けします。昼の時間と夜の時間、そして各エリアごとに小分けにしてお届けしていますので、京都の東山を観光しようと計画中の方はぜひモデルコースとしても参考にしてみてください!
あわせて読みたい

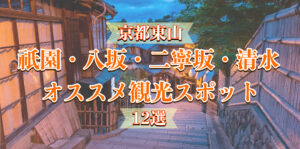
祇園・八坂・二寧坂・清水のおすすめ観光スポット12選! 京都東山の見どころ|所要時間・マップもどうぞ
京都随一の観光名所「祇園」。今回は周辺の八坂・二年坂(二寧坂)・清水エリアと一緒に着物で歩きたい東山のオススメ観光スポットをご紹介!インスタ映えな八坂の塔やカフェ、拝観時間や所要時間、料金やアクセス、夜のライトアップもマップと合わせてお届けです!
目次
昼の祇園・八坂エリア
まずは昼間の祇園・八坂エリアからご紹介していきます!
祇園と八坂神社
祇園への玄関口は「祇園四条」です!



四条大橋や河原町から一直線に進んだところにあるのが「八坂神社」です!










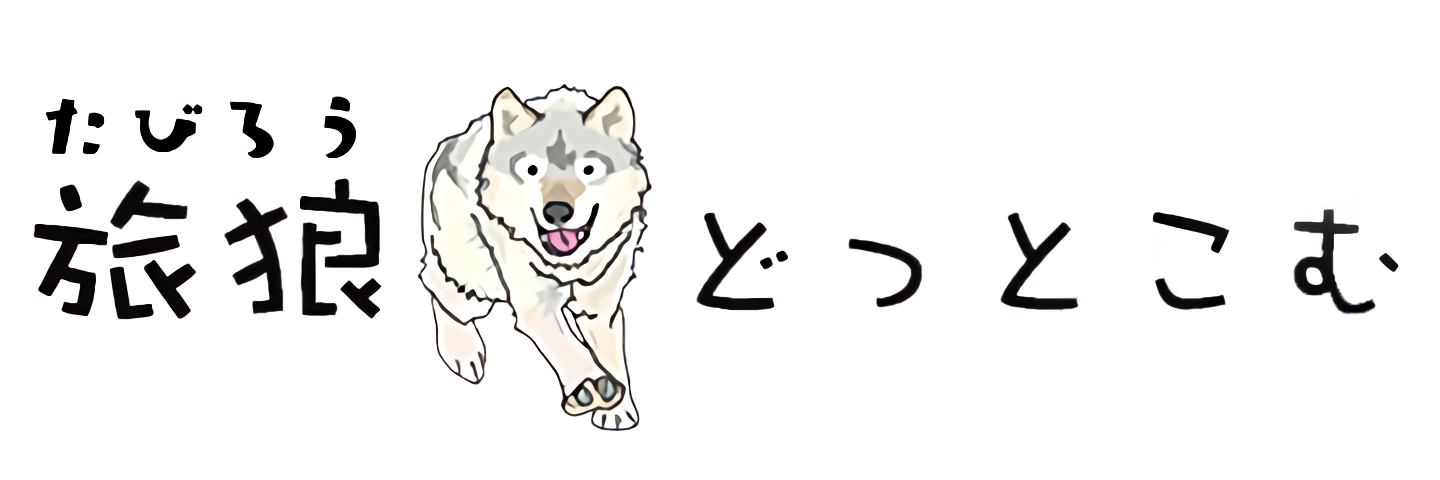


この記事へのコメントはこちらから!
コメント一覧 (3件)
[…] あわせて読みたい 【京都ひとり旅】東山エリアのモデルコースにどうぞ!祇園・八坂・二寧坂・清水の観光風景 京都旅行の観光名所にしてインスタ映えスポットが「祇園」を中心 […]
[…] だあなたへオススメ祇園・二寧坂・清水のオススメ見どころ紹介|京都らしいフォトスポットが満載の人気観光地👉 知恩院と合わせて行きたい見どころはコチラ! あわせて読みた […]
[…] あわせて読みたい 【京都ひとり旅】東山エリアのモデルコースにどうぞ!祇園・八坂・二寧坂・清水の観光風景 京都旅行の観光名所にしてインスタ映えスポットが「祇園」を中心 […]