みなさんこんにちは!観光情報サイト「旅狼どっとこむ」の旅狼かいとです!
今回の歴史雑学では、偉人「安倍晴明」をご紹介!
平安を代表する天文学者でありながら、非常に優秀な陰陽師でもあった安倍晴明。その高い能力と謎めいた半生から、現代でも文学やマンガ、アニメなどのモチーフにもなることが多い人物です。そんな安倍晴明の人物像や伝説、式神についてを深掘りしつつ、切っても切り離せない陰陽師ライバル「蘆屋道満」との関係についてもお話ししていきます!後半は陰陽師そのものについても簡単にお話しています。
少々堅苦しいお話もあるかもしれませんが、ぜひ身軽な気分で日本の歴史ロマンを彩る安倍晴明と蘆屋道満についてご覧になってください!
伝説上の安倍晴明はどんな人物?
早速、伝説上の安倍晴明についてお話していきましょう!
出生と歴史上の晴明

まずは安倍晴明の出生についてです。血筋としては、『竹取物語』にも登場する右大臣「阿倍御主人」や、遣唐使として唐に渡った文化人「阿倍仲麻呂」の子孫とする逸話が残されています。また、安倍晴明を祭神として祀る「晴明神社」の社伝では、晴明は孝元天皇の皇子「大彦命」の子であるとされています。
40歳の頃から、朱雀天皇から村上・冷泉・円融・花山・一条に至る計6代の天皇に側近として仕えていたといわる安倍晴明。村上天皇の時代には「遣唐使とともに唐へ渡り、城刑山にて伯道仙人の秘術を受け継いだ。そして帰国後、この秘術を元に日本独特の陰陽道を確立した」という逸話が残っています。
また、晴明を重用していた一条天皇が晴明の死後、「安倍晴明は稲荷神の生まれ変わりである」と言ったとも伝えられています。
『芦屋道満大内鑑』で登場する晴明

安倍晴明の伝説が有名になった作品として挙げられるのが、江戸時代中期の浄瑠璃『芦屋道満大内鑑』ですね!
歴史物語の『大鏡』や『十訓抄』、説話集の『今昔物語集』や『宇治拾遺物語』などに晴明の神秘的な逸話が記載されているのですが、そういった晴明の伝説を元にしてつくられた作品が『蘆屋道満大内鑑』なのです。
そんな作品の中で登場する「安倍晴明の母は「葛の葉」という白狐であり、その血を引く晴明は神がかった陰陽道の才を持つ子」という安倍晴明像が、「天才的な呪術を扱う晴明像」に結びついたと言われています。「葛の葉」は稲荷神(宇迦之御魂神)第一の神使とされていますから、非常に神聖な存在なのです。
そんな伝説における安倍晴明の能力として有名なのが、「セーマン(晴明桔梗・五芒星)」という呪符を用いた陰陽道と、式神「十二神将」ですね!
ということで、お次はこの2つについて深掘りしていきましょう!
安倍晴明のセーマン(晴明桔梗・五芒星)
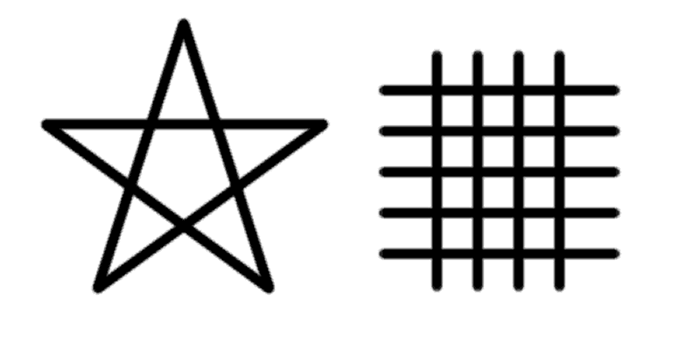
安倍晴明といえば「五芒星」、というイメージを持つ人も多いはず。あるいは「陰陽師」と「五芒星」を結びつけている方もるかもしれません。
そもそも「五芒星」のマークは、東洋・西洋にかかわらず世界的に魔術の記号として用いられている図形です。役割も実に様々で、守護に用いられることもあれば悪魔の象徴として用いられることもあります。
陰陽道における五芒星は、陰陽五行説の「木・火・土・金・水」の5つの元素の働きの相克を表したものであり、あらゆる魔除けの呪符として用いられています。
安倍晴明もまた、五行の象徴として五芒星を家紋に用いたとされています。ですので五芒星は、「晴明桔梗」や「セーマン」として晴明オリジナルというように見られることもありますが、基本的には陰陽道全般で用いられると言えそうですね。
ちなみに三重県の志摩地方には、海女が「セーマンドーマン」と呼ばれる模様をつけて漁をするという風習が残っています。これもまた、トモカヅキといった海の妖怪から身を守る魔除け的な意味合いだと言われています。
安倍晴明の式神「十二天将」

では、晴明のもう一つの能力と言える式神「十二天将」についてはどうでしょうか?
式神とは?
そもそも「式神」というのは、陰陽師が使役したとされる霊のことです。
「式鬼」とも書かれる式神は、その文字の通り神とも鬼とも言える存在。普段は和紙でできた札に封印されているのですが、術をかけると使用者の意図に合わせて自在に姿を変えたとされています。「人の善悪を監視する存在」とも言われ、今風にいうと「使い魔」に近いかもしれませんね。
「十二天将」とは?

そんな式神の中でも、安倍晴明が使役した12体の式神が「十二神将」とも呼ばれる「十二天将」です。
陰陽道における”本来の”「十二天将」とは、時刻をもとに天文と干支を組み合わせて占う「六壬神課」で使用するシンボルのようなもので、それぞれが十二支や方角と関連を持ちます。
六壬神課と安倍晴明が結びついた理由は、晴明が六壬神課の方法を『占事略决』という書物に記しているから。この中で十二天将が象徴するものを説明しているのです。逆にいうと、十二天将はあくまで占いの際に用いる「ツール」のようなものなので、直接的には霊とは関係ないんですね。
これは僕の推測ですが、物語の中でキャラクター性を付加しやすい十二天将がさも神や鬼のように扱われたのがきっかけなのではないかと思います。とはいえこれではロマンがないので、晴明が行使したという十二神将を簡単にご紹介していきます!笑
①騰蛇(とうだ・とうしゃ)
羽の生えた蛇の姿で炎を纏っていると言われます。安倍晴明には「主驚恐怖畏凶将」、「驚きや恐怖、畏れを司る凶将」と記されています。
- 五行:火
- 十二支:巳
- 吉凶:凶
- 陰陽:陰
- 方角:南東
②朱雀(すざく)

中国の四神(四獣)の一柱で、南の守護神である霊鳥「朱雀」と同一の存在とされています。炎を纏い翼を広げた赤い鳥の姿と言われます。晴明には「主口舌懸官凶将」、「おしゃべりな凶将」と記されています。
- 五行:火
- 十二支:午
- 吉凶:凶
- 陰陽:陽
- 方角:南
③六合(りくごう)
平和や調和を司る霊です。晴明には「主陰私和合吉将」、「隠し事や和合を司る吉将」と記されています。
- 五行:木
- 十二支:卯
- 吉凶:吉
- 陰陽:陰
- 方角:東
④勾陳・匂陣(こうじん・こうじん)
金色の蛇の姿をしており、京の守護を担っています。晴明には「主戦闘諍訟凶将」、「戦闘や激しい怒りを司る凶将」と記されています。
- 五行:土
- 十二支:辰
- 吉凶:凶
- 陰陽:陽
- 方角:南東
⑤青龍(せいりゅう)

中国の四神(四獣)の一柱で、東の守護神である「青龍」と同一の存在とされています。緑色の体と長い舌をもつ龍と言われます。晴明には「主銭財慶賀吉将」、「金銭や慶事を司る吉将」と記されています。
- 五行:木
- 十二支:寅
- 吉凶:吉
- 陰陽:陽
- 方角:北東
⑥貴人(きじん)
十二天将の主神で、「天一神」や「天一貴人」、「天乙」や「中神」など様々な呼ばれ方をします。天と地の間を往復し、四方を規則的に巡るとされる神です。平安時代には「貴人のある方角を犯すと祟りがある」と言われたことから、その時期に貴人がいる方角に直接向かうことを避ける「方忌み」が強く信じられていました。安倍晴明には「主福徳之神吉将大无成」、「福徳を司る吉将で主神」と記されています。
- 五行:土
- 十二支:丑
- 吉凶:吉
- 陰陽:陰
- 方角:北東
⑦天后(てんこう)
「媽祖」や「天妃」、「天上聖母」とも呼ばれる航海・漁業の守護女神です。中国の道教においては最も高位に位置する神であり、宋の時代の「黙娘」という女性が神になったという伝説が残っています。日本にもヤマトタケルの妃「弟橘媛」として伝わっており、晴明には「主後宮婦女吉将」、「天帝の后である吉将」と記されています。
- 五行:
- 十二支:亥
- 吉凶:吉
- 陰陽:陰
- 方角:北西
⑧太陰(たいいん・だいいん)
智恵に長けた老婆であるとされており、晴明には「主弊匿隠蔵吉将」、「隠し事を司る吉将」と記されています。
- 五行:金
- 十二支:酉
- 吉凶:吉
- 陰陽:陰
- 方角:西
⑨玄武(げんぶ)

中国の四神(四獣)の一柱で、北の守護神である「玄武」と同一の存在とされています。脚の長い大きな亀に蛇が巻きついた姿、あるいは尾が蛇である亀の姿と言われます。古代中国において、亀は「長寿と不死」の、蛇は「生殖と繁殖」の象徴とされており、この二つを合わせて「無病息災」と「子孫繁栄」を象徴しているともいわれます。晴明には「主亡遺盗賊凶将」、「終わりや盗みを司る凶将」と記されています。
- 五行:水
- 十二支:子
- 吉凶:凶
- 陰陽:陽
- 方角:北
⑩太裳・太常(たいじょう)
「四時の善神」とも呼ばれ、中国の最高神「天帝」に使える文官とされています。古代中国において実際に存在した官職でもあります。晴明には「主冠帯衣服吉将」、「冠と帯を着用し、きっちりとした服装の吉将」と記されています。
- 五行:土
- 十二支:未
- 吉凶:吉
- 陰陽:陰
- 方角:南西
⑪白虎(びゃっこ)

中国の四神(四獣)の一柱で、西の守護神である「玄武」と同一の存在とされています。細長い体をした白い虎の姿と言われます。晴明には「主疾病喪凶将」、「疾病や喪を司る凶将」と記されています。
- 五行:金
- 十二支:申
- 吉凶:凶
- 陰陽:陽
- 方角:南西
⑫天空(てんくう)
霧や黄砂を呼ぶと言われます。晴明には「主欺殆不信凶将」、「欺くことが殆どで信用できない凶将」と記されています。
- 五行:土
- 十二支:戌
- 吉凶:凶
- 陰陽:陽
- 方角:北西
蘆屋道満の歴史と伝説

ではお次は、安倍晴明最大のライバルと称される「蘆屋道満」についてご紹介していきます。
平安時代の陰陽師・呪術師として、「道摩法師」の名でも知られる蘆屋道満。道満が活躍したのは安倍晴明と同じく平安時代とされていますが、平安時代の文献ではその名はほとんど見ることができません。そのため「道摩法師と蘆屋道満は別人である」という説や「そもそも蘆屋道満という人物は実在していない」という説も存在するほどなのです。
江戸時代の地誌『播磨鑑』によると、蘆屋道満の出身は播磨国岸村(現在の兵庫県加古川市西神吉町岸)とあり、後世になって安倍晴明が伝説化されるとともに蘆屋道満も伝説化していったとされています。ですので「晴明のライバル」というイメージも、江戸時代ごろに語られた晴明像と共につくられていったと考えられますね。
そんな晴明のライバルたる道満ですが、その記述のほぼすべてで「正義の晴明」・「悪の道満」という扱いをされているのもまた特徴です。
安倍晴明と蘆屋道満の関係
では、安倍晴明と蘆屋道満の関係について紐解いていきましょう。
晴明と道満の関係をお話しする上では、二人が登場する物語を紹介しながら語るのが一番です。ここでは代表的な4つの作品を、完成したと考えられている年代が古い順に紹介していきます。
『簠簋内伝金烏玉兎集』(ほきないでんきんうぎょくとしゅう)

まずご紹介するのは、『簠簋内伝金烏玉兎集』です。
安倍晴明が幼少のとき、蘆屋道満と内裏で「争い負けた方が弟子になる」という呪術勝負を持ちかけたといいます。その場に居合わせた帝は、みかんを15個入れた長持を二人には見せずに持ち出させ、「中に何が入っているかを占え」というお題を与えます。
まずは道満が長持の中身を予測し「みかんが15個」と答えます。対する晴明は「鼠が15匹」と答えたのです。まわりでこの勝負の様子を見ていた大臣や公卿たちは安倍晴明が予想を当てられなかったと落胆します。
しかし長持を開けてみると、なんと中からは鼠が15匹出てきたのです。この結果、約束通り道満は晴明の弟子となったのでした。
その後、晴明は遣唐使として派遣され、長く唐の伯道上人のもとで修行をしていました。
そんな晴明の留守中、道満は晴明の妻と不義密通をしていました。そして晴明が唐から帰国後、道満は晴明に命を賭けた呪術による対決を申し込みます。このとき道満は、晴明が伯道上人から授かった書を盗み見て身につけた呪術を用い、晴明を殺害したのです。
しかし、第六感で晴明の死を悟った唐の伯道上人が来日し、呪術で晴明を蘇生させ道満を斬首。晴明は師から継いだ書を発展させ、日本における陰陽道の発展に貢献したのでした。
この『簠簋内伝金烏玉兎集』は安倍晴明が編纂した占いの実用書とされていますが、そもそも「晴明が伯道上人から授かった書」そのものが『簠簋内伝金烏玉兎集』であると考えられているため、実際は晴明の死後に作られたものだと言われています(物語そのものに、その物語が入っているというマトリョーシカみたいな状況なわけです笑)。
また、今日に伝わる「晴明の母はキツネだった」という『葛の葉伝説』は、江戸時代初期までにまとめられた注釈書『簠簋抄』において後述されたものとされています。
お次はそんな『葛の葉』の伝説をご紹介します。
『葛の葉』の伝説

村上天皇の時代、河内国に石川悪右衛門という男がいました。悪右衛門の妻は病気を患っており、治すのに苦労していました。そこで陰陽師である兄の蘆屋道満に占いをお願いします。そして道満の占いに従い、悪右衛門は和泉国にある「信太の森」へ赴き、野狐の生き肝を得ようとしました。
時を同じくして、摂津国に住んでいた安倍保名もまた信太の森を訪れていました。その時、保名は狩人に追われていた白狐を目撃し、狐を助けてあげました。
しかしこの際、保名は怪我を負ってしてしまいます。傷を負った状態でどう帰ろうかと考えていた保名の前に現れたのが、「葛の葉」という女性でした。葛の葉は保名を介抱して家まで送り届け、その後も見舞いに訪れます。そうして長い時を過ごす間に二人はいつしか恋仲となり、結婚し、「童子丸」という子供をもうけたのでした。
童子丸はすくすくと育っていったのですが、平穏な日々は童子丸が5歳のとき、突如として崩れてしまいます。葛の葉の正体が、保名に助けられた白狐であることが知られてしまったのです。葛の葉は、すべては稲荷大明神(宇迦之御魂神)の仰せである事を告白し、
「恋しくば 尋ね来て見よ 和泉なる 信太の森の うらみ葛の葉」
という和歌を残して信太の森へと帰っていったのでした。
保名は和歌の書き置きから、葛の葉は恩返しのために人間の世界に来たことを知り、童子丸とともに信太の森に向かいます。そして、姿をあらわした葛の葉から水晶の玉と黄金の箱を受け取り、別れることを決意したのでした。この時の水晶玉と黄金の箱は、葛の葉が稲荷大明神から「童子丸に授けるように」と任せられていた品だったのです。
それから数年後、童子丸は「晴明」と改名し、天文道を修め、母親の遺宝の力で天皇の病気を治し、陰陽頭に任ぜられました。しかし蘆屋道満に嵌められ、占いの力くらべをすることになります。最終的に晴明は道満を負かし、道満に殺された父の保名を生き返らせたのです。そして道満は首をはねられ、晴明は天文博士となったのでした。
『葛の葉』の伝説は江戸時代に入ると、後述する『芦屋道満大内鑑』という歌舞伎・浄瑠璃で描かれるようになります。今ではこの歌舞伎によって、安倍晴明の伝説として非常に有名なものとなっています。
また、「母である葛の葉が稲荷神の使いである」ということから、安倍晴明が稲荷神と同一視されているとも考えられています。
『宇治拾遺物語』 御堂関白の御犬晴明等奇特の事(巻14の10)
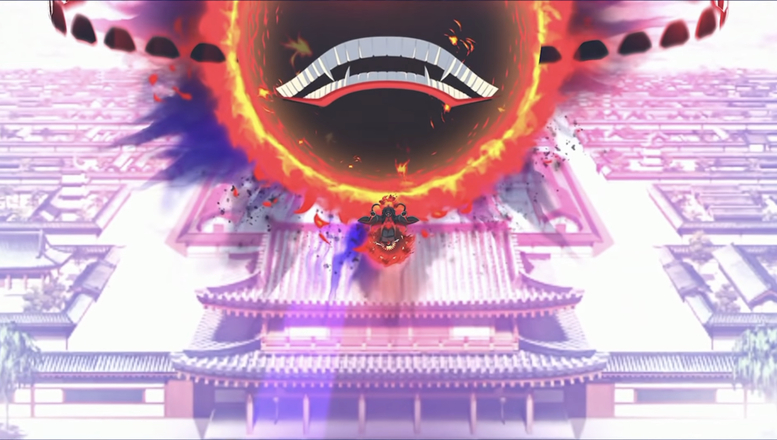
お次は『宇治拾遺物語』です。鎌倉時代前期に成立したとされる説話物語集で、収録されているお話が『十訓抄』や『古事談』といった『宇治拾遺物語』より前にまとめられた物語から着想を得たと考えられるものがほとんどなのが特徴です。そのため、当時よく語られていた物語、あるいは本当にあったお話のアレンジとも考えられています。
御堂関白藤原道長は法成寺を建ててから毎日、可愛がっていた愛犬と共にお堂へ出向いていました。そんなある日、道長がいつものように法成寺の門に入ろうとすると、愛犬は主人がそれ以上先に進めないよう強く咥えて引っ張ったのです。愛犬のあまりの必死な様子に驚いた道長は安倍晴明にことの仔細を占わせると、晴明は「道に殿下を呪うための呪物が埋められていたのを、犬が察知したのです」と伝えます。
さらに晴明は「こんな呪術を知っているのは道満以外いない」と考え、晴明は蘆屋道満を捕らえるよう道長に伝えます。
すぐに使いが遣わされ、道満は囚われの身となりました。そして道満は、「堀河左大臣顕光公に言われたのだ」と白状しました。道長は「本来は流罪に処すべきだが、道満の罪ではない。今後はこのようなことをしないように」と、道満を故郷である播磨国に流罪としたのでした。
ちなみにこの話の後日譚として、
堀河左大臣顕光(藤原顕光)は死後、藤原道長の家系に祟りをもたらしました。畏怖の念を込めて顕光は「悪霊左府」と呼ばれたのです。この祟りを目の当たりにした道長は、さらに愛犬を可愛がるようになったとさ。
という物語があります。
史実の上でも、「藤原顕光」は政権争いに敗れた藤原道長の家系を死後に呪い「悪霊左府」と呼ばれていたそうですから、道満が実在した可能性というのもあながち捨てきれないわけですね!
『峯相記』(ほうそうき、ぶしょうき)

『峯相記』は、南北朝時代初期の頃の播磨国の地誌になります。峯相山鶏足寺に参拝した旅中の僧が、お寺の僧から聞いたお話をまとめたものとされています。蘆屋道満の出身地が播磨国とされることから、この物語にも含まれたのだと推測できます。
摂関政治が行われていた時代、藤原道隆と藤原道長は関白の地位を争う政敵同士でした。
そんな中、道隆の嫡男である「藤原伊周」は蘆屋道満に、道長に対して呪詛をかけるための呪物を道に埋めるよう依頼します。
しかし、道満の呪詛は道長が信頼を寄せていた安倍晴明によって看破されてしまうのです。結局、道満は播磨国に追放され、その地で没したと伝えられています。
浄瑠璃・歌舞伎『芦屋道満大内鑑』(あしやどうまんおおうちかがみ)

ここまでの物語では、常に「善の晴明」「悪の道満」という描かれ方をしているのが特徴でした。しかし、江戸時代に活躍した竹田出雲の浄瑠璃『芦屋道満大内鑑』は、例外的に蘆屋道満が善人として描かれているのが特徴です。
『芦屋道満大内鑑』は、安倍晴明の出生譚である『安倍保名と葛の葉の物語』と『忠孝の士である芦屋道満が父殺しの悲劇を経て法師陰陽師となる経緯』が並行して語られる、「親子の愛情」というテーマのもと描かれた作品になっています。「葛の葉の物語」が母子の、「道満の物語」が父子の情愛を描く対称的な構造となっているのも特色として挙げられます。
そんな『芦屋道満大内鑑』は全5段構成なのですが、実は明治以降では省略なしで全段通しの上演が行われた記録がないのです。
「通し上演」と書かれていても3段目全部とその前後が省かれるのがほとんどなのですが、、この3段目の主役となるのが、何を隠そう芦屋道満なのです…!笑
結局残念な扱いをされてしまうのが道満の運命なのでしょうか。。
そもそも陰陽師とは?
安倍晴明の伝説と、蘆屋道満との関係について知っていただいたところで、お次は「そもそも「陰陽師」とは何なのか」をお話していきます。これを知っているかどうかで、日本史における陰陽師のイメージが結構変わってくるのです。
陰陽道とは?
まず「陰陽”師”」とは、「陰陽”道”を扱う人」のことです。そして「陰陽道」とは、占いや天文、時間や暦の編纂を担当する部署「陰陽寮(おんようのつかさ、とも)」で学ばれていた”技術”になります。
「〇〇道」という言葉は現代の私たちからするとあまり馴染みがなく、ともすれば「思想や宗教体系の一つ」みたいなイメージを持つ人もいるかもしれません。ですが「〇〇道」というのは今風にいうと「〇〇学」に近いニュアンスになり、主に技術体系を指す言葉なのです。
実際、陰陽寮では陰陽道の他にも、暦を作成するための学問だった「暦道」や天文現象の異常を観測・記録し、地上への影響について研究する「天文道」なども教えられていたそうです。「陰陽寮」という専門学校があり、その中の専攻の一つとしての「陰陽道」というわけなのです。

陰陽師の起源
そんな陰陽道の起源は、中国の春秋戦国時代に現れた学者の学派「諸子百家」の一つ「陰陽家」にあるとされています。
陰陽家の考え方は「世界の万物の生成と変化は陰と陽の二種類に分類される」という「陰陽思想」にあり、この陰陽思想がのちに、「万物は木・火・土・金・水の五行からなる」とする「五行思想」と組み合わさって「陰陽五行思想」が完成します。この陰陽五行思想が古墳時代〜飛鳥時代の日本に伝わり、独自の発展を遂げたものが「陰陽道」なのです。
蘇我馬子や聖徳太子の時代に、朝鮮半島から仏教思想が取り入れられた日本。実はこのときに陰陽五行思想も一緒に中国・朝鮮半島から伝わっており、聖徳太子の冠位十二階や十七条憲法にもその思想が反映されていると言われています。そして、天武天皇(大海人皇子)が676年に、陰陽寮や日本初の占星台を設置したのです。この頃から、陰陽寮に属し陰陽道に関わる者を「陰陽師」と呼び始めたとされています。
初期の陰陽師たちは、暦や時間の管理、天体観測、陰陽五行に基づく論理的な分析によって、”純粋な”占筮や占星、地相(現在で言う「風水」のようなもの)による予言をしており、神祇官や僧侶のような宗教的な儀式や祭儀、そして呪術はほとんど行なっていませんでした。それでも、朝廷・宮中における吉日選定や、土地・方角などの吉凶を占うことで遷都の際などには重要な役割を果たしていたのです。
陰陽師の魔術・呪術的なイメージはいつから?

では、陰陽師が現代よく持たれる「魔術」や「呪術」のイメージに近くなったのはいつ頃、どんなことがきっかけだったのでしょうか? これには平安時代に起こった具体的な事件が関わっています。
延暦4年(785年)に起こった「藤原種継の暗殺事件」。首謀者として考えられた十数人が死罪や流罪に処されたのですが、その全容が明らかとなることがなかった事件としても知られています。そんな事件で流罪に処された者の一人に、皇族である「早良親王」がいます。
早良親王は無実を訴え、抗議の意を示すために絶食、その流れて死んでしまいました。すると早良親王の死後、早良親王を陰謀によって嵌めたともされる桓武天皇の身辺に禍ごとが頻発。「これは親王の祟りではないか」と世の中に恐れが広がります。
結局、怨霊におびえ続けた桓武天皇は長岡京から平安京への遷都を決意したのですが、この祟りや遷都がきっかけとなり、それまで影響力の小さかった御霊信仰が朝廷・貴族社会に広まり、悪霊退散のために呪術によるより強力な恩恵を求める風潮が強くなったと考えられているのです。
その中で、朝廷や貴族に占いとして重用されていた陰陽道において呪術的な色合いが強まり、加えて宗教のような要素も帯びるようになったのです。
こうして陰陽道を司どる陰陽師は、室町時代後期まで政治と密接な関わりを持つことになります。室町時代以降は日本が戦国の世と化します。「武」がものをいう時代においては、占いや呪いも廃っていったというわけですね。
安倍晴明の史実としての歴史

ではここで、安倍晴明の史実上の歴史をご紹介していきます。
実は晴明の伝説ができた背景には、史実における晴明の素晴らしい陰陽師の能力や陰陽道による実績、天皇家からの特別な扱いから、後世で次第に神秘化されたことによる点が大きいのです。伝説は物語的な要素が大きいのでそこを掘り返すのは野暮ではありますが、、せっかくの機会なのでリアルな晴明の人物像もご紹介しますね!
出生と幼少期
安倍晴明の出生については、明確な記述が残っていないと言われています。
有力な説によると、催事の際の食事を担当する役職に就いていた「安倍益材」、あるいは淡路守の「安倍春材」の子とされています。幼少時代についても確かな記録は残されていませんが、陰陽師の「賀茂忠行・保憲」父子のもとで陰陽道を学び、天文道を身につけたと伝えられています。
遅咲きの天才
安倍晴明について明確な記述があわられるのは、晴明が40歳ごろのものからです。陰陽寮で陰陽道を学ぶ身であった晴明は、960年に村上天皇に占いを命じられています。天皇から命が下されるというのはかなりの信頼の証ですから、40歳と遅咲きであるものの、能力は貴族から認められていたと考えられています。
天皇家から晴明への信頼は、当時59歳の晴明が皇太子「師貞親王(後の花山天皇)」の命で那智山の天狗を封じる儀式を行なったところからさらに篤くなったといわれており、実際、この出来事以降の記録では、晴明が占いや陰陽道の儀式を行った様子が多く見られるようになります。花山天皇が退位した後も、一条天皇や藤原道長といった貴族世界の重鎮たちの信頼を集め続け、晴明についての記述が道長の日記『御堂関白記』や藤原実資の日記『小右記』にたびたび記されています。
中には、「一条天皇が急な病に伏せったときに晴明が禊を奉仕したところ、天皇の病がたちまち回復した」や「寛弘元年(1004年)7月、深刻な干魃が続いたため晴明に雨乞いの五龍祭を行わせたところ、一気に雨が降り、これを一条天皇は晴明の力によるものと認め被物(かずけもの)を与えた」といった、晴明の神がかりな陰陽道の能力が垣間見える記述も残されています。
陰陽師として名声を極めた晴明は、天文道で培った計算能力をかわれて税収を把握・監査する主計寮に異動し、主計権助を務めます。そして様々な官職を歴任したのち、位階は朝廷におけるNo.10「従四位下」にまで昇りつめました。一見凄さがわかりにくいですが、出身・家柄が重視される平安時代において、これは非常に稀な出世です。
晴明自身の大きな出来事しては以上ですが、以降の時代では晴明の2人の息子である「安倍吉平」と「安倍吉昌」も父の跡を継ぐ形で天文博士や陰陽頭に任ぜられています。このことから、安倍晴明は自身一代で、「安倍氏」の陰陽師としての地位を師である賀茂氏に並ぶところにまで押し上げたと言われているのです。
どうやら史実としての安倍晴明は、「遅咲きの天才」というイメージがピッタリなようですね!
安倍晴明を祀る神社「晴明神社」


ここまでご紹介してきた安倍晴明と蘆屋道満、そして二人に密接に関わる陰陽道。実は安倍晴明を”祭神”として祀る神社が、日本にはいくつかあるのです。そのうちの一つで有名なのが、京都の「晴明神社」です。
境内の至るところに現在は神社の社紋となっている「晴明桔梗」こと「五芒星」が記されており、普通の神社ではないような不思議な雰囲気を感じる場所になっています。近くには、『渡辺綱と鬼女の伝説』や『晴明の式神伝説』、「死者の復活」といった多くの怪異譚が語られてきた”曰く付き”スポット「一条戻橋」もあり、パワースポットとしても有名な場所となっています。
安倍晴明に興味を持っているという方は、ぜひ京都の晴明神社にも足を運んでみてくださいね!


安倍晴明と蘆屋道満 まとめ


ということで今回は、平安を代表する陰陽師「安倍晴明」の伝説や式神、そしてライバル「蘆屋道満」についてとその関係ご紹介してきました!
FGOや呪術廻戦といったアニメや漫画からこの記事に来た方も多いと思います。そういった現代の作品から歴史や偉人に興味を持って史実や伝説を調べてみるというのは、自分の知見を広げるためにとても良い機会となるでしょう。
それを知っていることで、雑学が増えたり旅行にいった際のうんちくが増えたりして、より様々なことが楽しくなること間違いなしですからね! ぜひ今回にとどまらず、さまざまな人物や歴史の物語を調べてみてくださね!


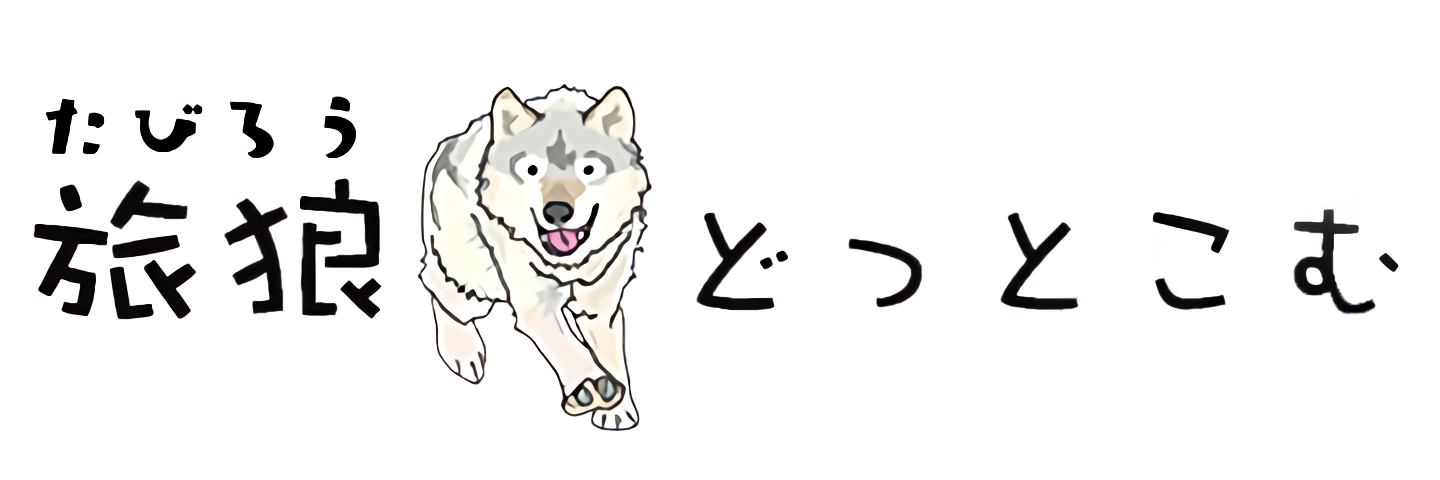


この記事へのコメントはこちらから!
コメント一覧 (3件)
[…] 👉 平安時代の歴史・伝説に興味があるなら、安倍晴明も要チェック! […]
[…] 👉 京都らしい独特な歴史が好きな方はこちらもチェック! 平安浪漫の一人「安倍晴明」 […]
[…] 👉 神話や物語に興味がある方はコチラもおすすめ! 安倍晴明と蘆屋道満 […]