みなさんこんにちは! 観光情報サイト「旅狼どっとこむ」の旅狼かいとです!
今回ご紹介するのは、「古都京都の文化財」の一つとしてユネスコの世界文化遺産に登録されている嵐山の「天龍寺」です!
天龍寺といえば、「どこから見ても天井に描かれた龍がこちらを睨んでいるようにみえる」という「雲龍図」や京都屈指の庭園「曹源池庭園」の紅葉でとても有名ですが、、見どころはそれだけではないのですよ!
そんな天龍寺について、知っていると旅行が面白くなること間違いなしの歴史や魅力、拝観時間や拝観料、特別拝観やアクセスなどの情報をお届け! 嵐山観光の前にぜひご覧ください!
天龍寺の歴史
まずは天龍寺の歴史をご紹介します!
天龍寺が建立される前のお話

天龍寺の正式名称は「霊亀山天龍資聖禅寺(れいぎざんてんりゅうしせいぜんじ)」といい、嵯峨天皇の皇后である「橘嘉智子(檀林皇后)」が開創した禅寺「檀林寺」が大元になっています。
やがて檀林寺は廃れてしまうのですが、後嵯峨天皇とその皇子である亀山天皇が檀林寺があった場所に離宮として「仙洞御所」を造営し、のちに上皇となった亀山上皇が「亀山殿」として利用しました。
そしてその後、亀山殿の跡地に建てられたのが「天龍寺」なのです!
※ちなみに、「亀山」というのは嵐山に聳える「小倉山」のこと。山の形が亀の甲に似ていることから付けられた名前だそうですよ!
天龍寺の建立 ~夢窓疎石の活躍~

天龍寺は、暦応2年(1339年)に室町幕府を開いた「足利尊氏」が「夢窓疎石」を開山として建立したお寺になります。
その目的は「後醍醐天皇の菩薩を弔うため」なのですが、、これを聞いた歴史好きの方はこう思うかもしれません。
「え、尊氏が後醍醐天皇を祀るの??」
そう。足利尊氏は、後醍醐天皇が推し進めた「建武の新政」に叛旗をひるがえし、事実上瓦解させた張本人。一応一緒に鎌倉幕府を打倒した仲ではあるのですが、最終的には敵同士となった2人なのです。
ではなぜ、足利尊氏は後醍醐天皇を祀る寺院を建てたのでしょう? そこには当然第三者の影響があるわけで、尊氏に後醍醐天皇を弔うよう強く勧めたのが「夢窓疎石」だったのです。

当時、禅僧として武士の人々から多大な尊崇を受けていた夢窓疎石は、10代後半の時から鎌倉や奈良、そして京都など日本列島を行き来しならがらその時々でお寺に属し、そのうち何度かはお寺の復興も果たしたお坊さまでした。こうした功績が後醍醐天皇によって認められ、天皇の詔によって京都臨川寺開山や南禅寺住持に就任し、最終的には「夢窓国師」の号を下賜されるにまで至ったのでした。
こういった経緯から、夢窓疎石は後醍醐天皇に恩義を感じていたのでしょう。後醍醐天皇なき時代の日本の覇者となった足利尊氏に、後醍醐天皇を弔うよう勧めたのでした。
天龍寺の発展

夢窓疎石の勧めにしたがい、足利尊氏は後醍醐天皇を祀るために天龍寺建立を計画。当初は造園費用が不足してしまうという問題も抱えますが、「天龍寺船」と呼ばれた貿易船を利用した中国(元)との貿易を再開したことで収入を確保。
無事に建立された天龍寺はその後、足利将軍家と後醍醐天皇ゆかりの禅寺として京都五山の第一位となったのでした。

最大規模を誇った際は、西は嵐山や渡月橋、東は現在の嵐電帷子ノ辻駅あたりまで広がる広大な境内を有していた天龍寺。8度にも及ぶ度重なる火災や兵火に見舞われるもののその度に再建・復興を果たし、現在の姿となりました。
現代に入ると、御所が発端となった歴史や後醍醐天皇を弔ったという創建、そして美しい曹源池庭園の風景から、日本で最初に史跡・特別名勝に指定されます。そして1994年(平成6年)12月には、「古都京都の文化財」の構成資産の一つとしてユネスコの世界文化遺産に登録されたのでした。
天龍寺の見どころ
それでは、天龍寺へ足を運んだら絶対に見ておきたい見どころをご紹介します!
曹源池庭園

天龍寺一番の見どころと言えるのが、この「曹源池庭園」でしょう!
嵐山や亀山(小倉山)を借景にして中央の曹源池を巡る池泉回遊式である曹源池庭園は、天龍寺の開山である夢窓疎石が作庭したと伝えられています。
お寺のほとんどが明治時代に再建されている天龍寺ですが、この曹源池庭園は今なお創建当時の趣を残しているとして、嵐山のみならず京都屈指の庭園として知られていますよ! 日本初の史跡・特別名勝に指定された理由や世界遺産の構築資産として加えられた理由として、この曹源池庭園の存在が挙げられるほどですからね!

秋には紅葉に染まる風景を楽しめるが何よりの魅力ですが、見る場所によって多くの”見方”を楽しむことができるのも曹源池庭園のポイント! 庭園に臨む天龍寺最大の建物である大方丈から眺めるもよし、隣の書院である小方丈から眺めるもよし、庭園におりて見てまわるもよしです!
龍門の滝

また、方丈から曹源池庭園を眺めるとちょうど曹源池中央正面に見える「龍門の滝」も見どころの一つです!
一枚の巨岩(鯉魚石)を用いて鯉が滝を登る様子を表現することによって、「出世や成功のための関門を通ること」を意味する中国の故事成語「登龍門」を表したものになります。
実は、岩によって登龍門を表現する「龍門の滝」そのものは多くの庭園で採用されています。しかし、一般的には鯉魚石が滝の下に置かれているのに対し、天龍寺の鯉魚石は滝の流れの横に置かれており、鯉が龍と化す途中の姿を現しているという珍しい姿なのが特徴です。
方丈の縁側には座ることもできるので、ここで旅の合間の一息をつきながらのんびりと庭園の解釈を広げてみるのもおもしろいですよ!
百花苑

方丈や曹源池庭園からさらに奥に進んだところに広がるもう一つの庭園が「百花苑(ひゃっかえん)」です。昭和58年(1983年)に北門開設と同時に整備された庭園で、天龍寺の裏山の自然の傾斜に沿って苑路が造られているのが特徴です!
“百花”という名前のイメージ通り四季折々の木々が植えられており、春は桜、夏は蓮や桔梗、半夏生(はんげしょう)や百日紅(さるすべり)などを愛でることができます。もちろん、秋の紅葉の時期は曹源池庭園とともに多くの観光客が足を運ぶ人気の名所です!

ちなみに、天龍寺の北門を抜けると、嵐山随一の観光名所である「竹林の小径」や、紅葉の名所・百人一首の聖地として知られる「常寂光寺」などへと進むことができますよ!
方丈

大方丈と小方丈(書院)からなる天龍寺の方丈。天龍寺最大の建物である大方丈は明治32年(1899年)、小方丈は大正13年(1924年)にそれぞれ再建されたものになります。
大方丈の本尊は釈迦如来坐像。これは平安時代後期の作とされているため、室町時代初期に建立された天龍寺そのものよりかなり昔のものなのが特徴ですね!
天龍寺は過去八度もの火災にみまわれているものの、そのすべてで守られてきたという何か特別な”パワー”を感じる仏像でもありますね!
祥雲閣と甘雨亭

「祥雲閣(しょううんかく)」と「甘雨亭(かんうてい)」は、方丈から多宝殿へ上る廊下の右手にある茶室です。
祥雲閣・甘雨亭ともに、昭和9年(1934年)に後醍醐天皇の尊像を安置する多宝殿を建立した際にその記念事業として建築されました。

祥雲閣は、わび茶を大成した千利休が開祖である本家の流派「表千家」の茶室「残月亭」を模したもので、12畳敷きの広間に2畳の上段の間を床の間とする様式となっています。
対して甘雨亭は4畳半台目の茶室で、通い口前に三角形の鱗板をつけているのが特徴。本家の表千家に対して、分家である裏千家の14代家元「淡々斎」によって名付けられた茶室になります。
※台目畳:通常の丸畳の4分の3の大きさの畳のこと
多宝殿

小方丈から右手に祥雲閣や甘雨亭の茶室が見える屋根付きの廊下を上がるとあるのが「多宝殿」になります。
後醍醐天皇の尊像が祀られている祠堂であり、どこか中世の貴族屋敷を思わせる雰囲気が特徴です。正面に広がる百花苑から見下ろせば、多宝殿全体を見ることもできますよ!
昭和9年(1934年)に建てられた建物であり、亀山上皇が離宮として使用していた際に、この場所を後醍醐天皇が学問所としていたと言われています。
雲龍図(法堂)

どこにいても龍に睨まれているように見える「八方睨み」で有名なのが、「法堂(はっとう)」の天井に描かれた「雲龍図」ですね!
縦10.6m・横12.6mの天井に厚さ3cmの檜板159枚を張り合わせた全面に漆と白土を塗り重ねた下地に、直径9mの二重円相に囲まれた龍の絵が直接墨色で描かれています。緻密ながらも生き生きと描かれており、思わず「オォ」と唸ってしまうほどの躍動感でした!(写真撮影は禁止となっています!)
現在の雲龍図は、平成9年に「天龍寺開山夢窓国師650年遠諱記念事業」として日本画家「加山又造」によって描かれたもの。明治時代の再建時からそれまでは紙に書いたものが天井に貼ってあったそうなのですが、損傷がひどく修復ができなかったそうです。
法堂の雲龍図、通常時は土曜日・日曜日・祝日のみの公開ですので、平日を狙って観光をする方は注意してくださいね!(春・夏・秋の特別参拝の期間は毎日公開されます。)
※紙に書かれていたもともとの雲龍図はその一部が保存されており、2022年は2月5日(土)〜4月10日(日)の期間で大方丈で一般公開されていますよ!
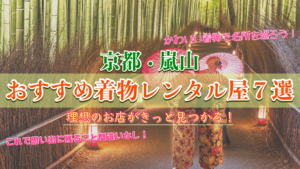
天龍寺の観光地情報
それでは、天龍寺の拝観時間や拝観料、特別拝観の日程やアクセス情報などをご紹介します。
拝観時間

【庭園(曹源池・百花苑)】
8:30~17:00(最終受付は16:50)
【2022年の曹源池庭園の早朝参拝】
11月12日(土)~11月30日(水)
7:30から拝観が可能となります
【諸堂(大方丈・書院・多宝殿)】
8:30~16:45(最終受付は16:30)
※10月29日の午前中と30日の午前中は休館日
料金

【庭園(曹源池・百花苑)】
・高校生以上:500円
・小・中学生:300円
・未就学児 :無料
【諸堂(大方丈・書院・多宝殿)】
・庭園参拝料に300円追加
雲龍図(法堂)について
公開期間
【通常期間】
土曜日・日曜日・祝日
※行事等により参拝出来ない日あり
【2022年の特別参拝(毎日公開)】
春:1月29日(土)〜7月31日(日)
夏:8月6日(土)~8月16日(火)
秋:9月10日(土)~12月4日(日)
参拝休止日:1月1日~2日、10月28日~30日

拝観時間
9:00~16:30(受付終了は16:20)
料金
500円(庭園・諸堂とは別料金)
紅葉の見頃

・色づき始め:11月中旬
・見頃:11月下旬~12月上旬
桜の見頃
3月下旬~4月中旬
観光のオススメ時間と所要時間
・おすすめ時間:開館直後
・所要時間:60~75分
アクセス

〒616-8385
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68
TEL:075-881-1235
【電車】
・京福電鉄嵐山線(嵐電)「嵐山駅」からすぐ
・JR嵯峨野線「嵯峨嵐山駅」下車後、徒歩13分
・阪急電車「嵐山駅」下車後、徒歩15分
【バス】
・市バス11、28、93系統「嵐山天龍寺前」で下車後すぐ
・京都バス61、72、83系統で「京福嵐山駅前」で下車後すぐ
【駐車場】
・120台ぶん完備
・利用可能時間:8:30〜17:00
・乗用車料金:1回1,000円
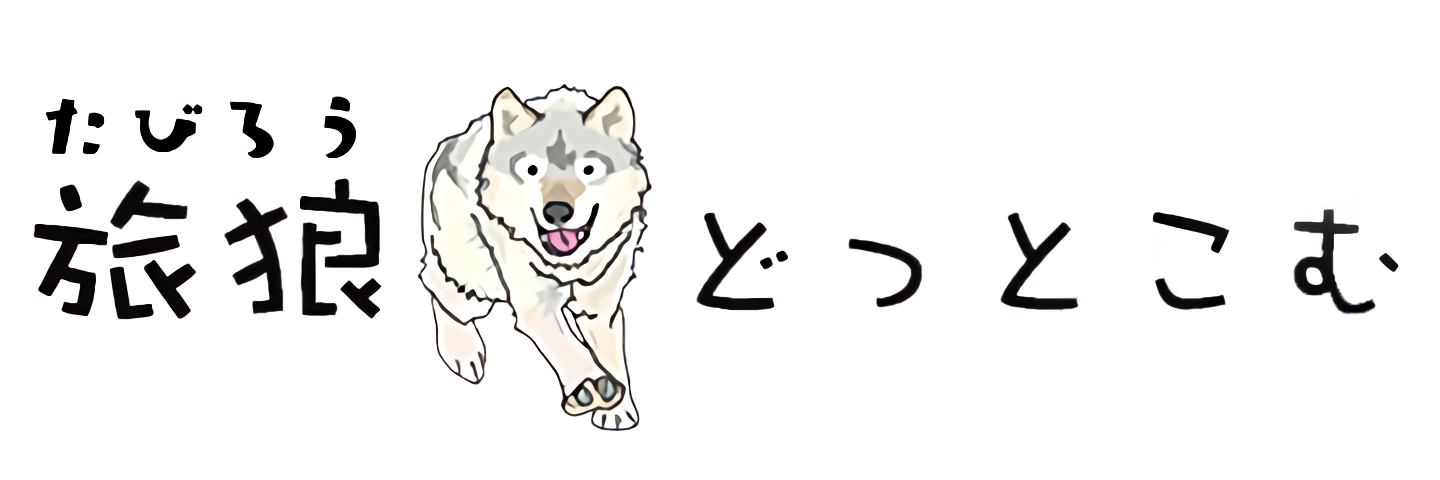


この記事へのコメントはこちらから!
コメント一覧 (3件)
[…] 👉 天龍寺の見どころや歴史、拝観料など詳しくはコチラ! […]
[…] 「登龍門」を表現した岩は天龍寺の曹源池庭園や金閣寺の庭園をはじめ数多くの禅宗庭園に見られ、修行僧の心の支えとなる修行に励むためのシンボルだったそうですよ! […]
[…] 天龍寺や野宮神社といった歴史と伝統ある寺社仏閣や、1000年以上人々を魅了し続ける竹林の小径など観光名所が満載の嵐山においては、キモノフォレストはかなり現代的な見どころとな […]