みなさんこんにちは! 世界・日本の観光地や旅行情報、歴史や雑学をご紹介している旅狼かいとです。
今回のブログでご紹介するのは、秋の京都において「南禅寺・永観堂エリア」と呼ばれる地域の紅葉情報です!
このエリアの名前となっている「南禅寺」と「永観堂」は毎年世界中から観光客が押し寄せる超人気の二大紅葉スポット!
ここではそんな南禅寺と永観堂に加え、古くから続く古都京都の庭園の面影を残す「南禅院」、趣がまったく異なる二つの庭園を一度に味わえる「天授庵」、四季折々の日本の自然を楽しめる散歩道「哲学の道」も加えた選りすぐりの5選の歩き方をお届けします!
目次
南禅寺

日本最初の勅願禅寺である「南禅寺」。京都五山と鎌倉五山の上に位置する「別格上位」、つまり、日本のすべての禅寺の中で最も格式が高い寺院となります。
現在の南禅寺が建つ地には、もともと「禅林寺殿」という離宮がありました。しかし亀山法皇の時代、妖怪たちが毎夜毎晩現れ大層迷惑を被ることになってしまいます。
そこに現れたのが「無関普門(大明国師)」という僧でした。弟子を連れて禅林寺殿を訪れた無関普門は、なんとなんと坐禅を組むだけで妖怪たちを退治してしまったのです! どこぞのマンガかよ!と突っ込みたくなるほどのお坊さんですね。。
ともあれこの出来事から、亀山法皇は無関普門を開山として禅林寺殿を「龍安山禅林禅寺」という名前の寺に改めました。
その後、現在の名称である「南禅寺」(正式には「太平興国南禅禅寺」)となり、後醍醐天皇によって五山の第一位とされます。さらに、足利義満によって京都五山と鎌倉五山の上位に当たる最上位「別格上位」に位置付けられ、南禅寺は隆盛を極めます。
しかし、京都を火の海とした「応仁の乱」で、南禅寺は伽藍をはじめとする境内のほとんどが焼失してしまいます。
なかなか再建が進まなかった南禅寺でしたが、徳川家康の時代に「黒衣の宰相」と呼ばれた「以心崇伝(いしんすうでん)」という僧の政策によって復興を果たし、現在の姿となりました。(「以心崇伝」は「僧侶にして政治家」という、またも風変わりなお坊さん。南禅寺はこうしたお坊さんとの縁もあるのでしょうかね。。笑)
明治維新後には、境内に「琵琶湖疏水水路閣(レンガ造りの水道橋)」が造られ、今日でも南禅寺の見どころの一つとなっていますね!

他にも、歌舞伎『山門』で石川五右衛門が言い放つ「絶景かな、絶景かな」の舞台である「三門」や、虎が子虎を連れて川を渡る様子を表現した「虎の子渡しの庭」として有名な「方丈庭園」など、見どころが目白押しの南禅寺!
「歴史も深く見どころも満載!」ということは、当然人も多い!笑
ゆっくりと自分のペースで寺院を味わいたい方や、写真をこだわって撮りたいという方は、朝一番での訪問をオススメしますよ!
南禅寺の観光案内

拝観時間
境内は自由散策
【3月1日~11月30日】
8:40~17:00(受付終了は16:40)
【12月1日~2月末】
8:40~16:30(受付終了は16:10)
※12月28日~12月31日の年末は、一般拝観はできない。
拝観料(方丈庭園・三門)
・大人:600円
・高校生:500円
・小中学生:400円
※方丈庭園と三門は別料金
紅葉の見頃とオススメの観光時間

・色づき始め:11月中旬
・見頃:12月上旬
【オススメの観光時間】
早朝~午前中
アクセスと駐車場
〒606-0000
京都府京都市左京区南禅寺風呂山町86-5 南禅院
・地下鉄「蹴上駅」から徒歩10分
【駐車場】
50台ぶん完備(南禅寺の駐車場)
・2時間以内:1,000円
以降1時間ごとに+500円
👉 南禅寺についてさらに詳しくはコチラ!
あわせて読みたい
【京都観光】レンガ造りの水路閣と圧巻の三門!南禅寺の見どころ・歴史・アクセス・拝観料など
今回は京都随一の観光スポット「南禅寺」をご紹介!レンガ造りの水路閣と石川五右衛門の三門がシンボル。春は桜、秋は紅葉の名所としても人気の見どころや歴史、拝観料やアクセスと駐車場、ライトアップ情報やモデルコースを写真と一緒に簡単にわかりやすくお届けします!
南禅院

「南禅院」は、南禅寺の境内の一角にある京都の隠れた名所です! 目の前には明治時代に造られたレンガ造りの水道橋が建っており、いわば南禅寺境内の”最深部”にあたるところに位置します。
上述の南禅寺のところでも紹介しましたが、現在南禅寺が建つ場所にははもともと、後嵯峨天皇が造営した離宮「禅林寺殿」が建てられていました。禅林寺殿は「上の御所」と「下の御所」に分かれており、上の御所に建設された持仏堂が「南禅院」と呼ばれており、「”今日の”南禅院」は「”かつての”南禅院」の後身となります。
言うなれば”離宮の遺跡”であり、「南禅寺発祥の地」ともされるのがこの南禅院なのです!

現在の方丈は、徳川綱吉の母「桂昌院」の寄進によって再建されたもの。池泉回遊式の庭園は京都三名勝史跡庭園の一つに数えられ、京都に唯一残る鎌倉時代末期の名庭になります。
亀山法皇自ら作庭したとも伝えられる庭園は、南禅寺境内の喧騒が嘘のようにひっそりとしており、静謐かつ幽玄な空間となっていました。何となく、『風の谷のナウシカ』や『もののけ姫』を彷彿とさせる雰囲気でもあったように思います…!
一つの境内にこれほど雰囲気が違う場所があるというのも不思議なものですが、それがまたこの庭園の”味”になっているのかもしれませんね!
南禅院の観光案内

拝観時間(南禅寺と共通)
【3月1日~11月30日】
8:40~17:00(受付終了は16:40)
【12月1日~2月末】
8:40~16:30(受付終了は16:10)
※12月28日~12月31日の年末は、一般拝観はできない。
※屋根葺き替えのため、南禅院は2023年(令和5年)12月4日~2025年(令和7年)の期間で臨時休業中です。
拝観料
・大人:400円
・高校生:350円
・小中学生:250円
紅葉の見頃とオススメの観光時間

・色づき始め:11月中旬
・見頃:12月上旬
【オススメの観光時間】
比較的穴場
アクセス(南禅院と共通)
〒606-0000
京都府京都市左京区南禅寺風呂山町86-5 南禅院
・地下鉄「蹴上駅」から徒歩10分(南禅寺境内の一部)
・駐車場は南禅寺のものを使用









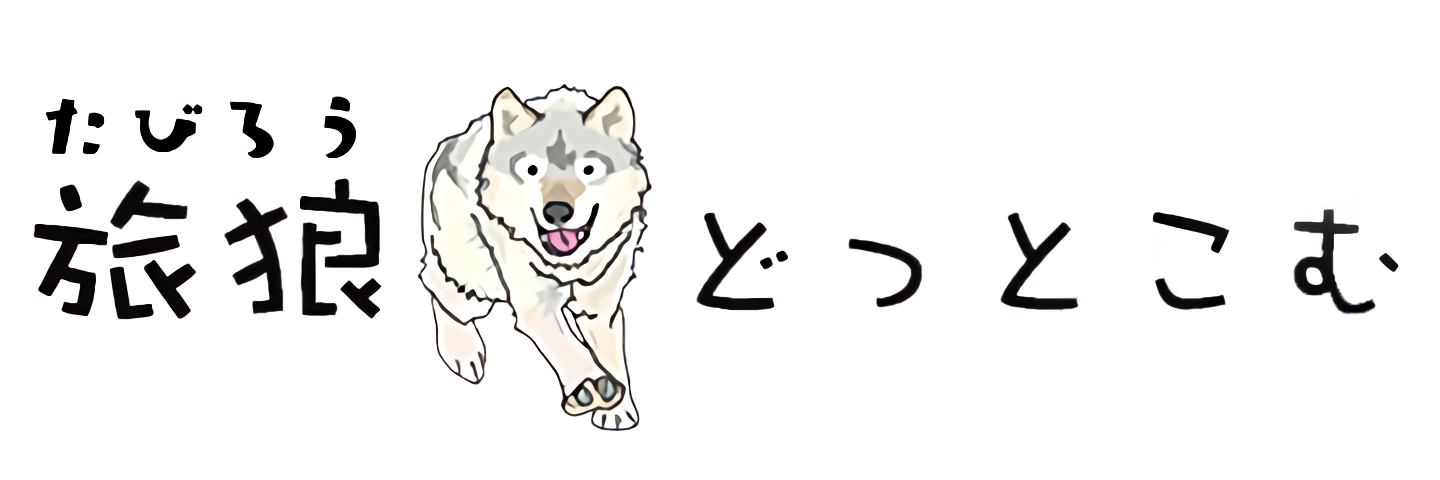

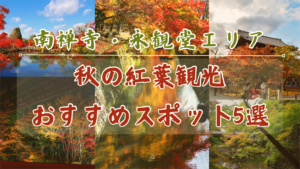
この記事へのコメントはこちらから!
コメント一覧 (3件)
[…] 👉 永観堂と一緒に巡りたい、永観堂エリアの紅葉名所はコチラ! […]
[…] すすめ紅葉スポットも要チェック! 【2024秋】南禅寺・永観堂周辺でオススメ!紅葉の見どころ名所5選|見頃・ライトアップ・特別拝観・拝… このブログでは京都旅行の紅葉スポ […]
[…] おすすめの紅葉スポットはコチラ! 【2024秋】南禅寺・永観堂周辺でオススメ!紅葉の見どころ名所5選|見頃・ライトアップ・特別拝観・拝… このブログでは京都旅行の紅葉スポ […]