みなさんこんにちは! 世界・日本の観光地や旅行情報、歴史や雑学をご紹介している旅狼かいとです。
今回は京都市街地の北部に位置する「上賀茂神社」をご紹介します!
正式名称を「賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)」という上賀茂神社は、京都でも最古とも言われるその歴史から「京都最古の最強パワースポット」とも紹介される名スポット。「賀茂神社」として上賀茂神社の南に位置する下鴨神社とともに「古都京都の文化財」の一部として世界文化遺産にも登録されており、実際に足を運んでみると、筆者も本当に不思議な雰囲気を感じたのです…!
そんな京都の中でも屈指の歴史と神性を誇る上賀茂神社について、歴史や見どころ、アクセスなどの旅行の際に知っておきたい情報、さらに京都三大祭りでもある例祭「葵祭(賀茂祭)」についてもお届けしていきます!
上賀茂神社の歴史
まずは観光前に知っておきたい上賀茂神社の歴史をご紹介します。
創建伝説

上賀茂神社の創建については諸説ありますが、ここでは社伝として伝わる『山城國風土記逸文』の『賀茂舊記』に記されている内容をご紹介します。
神代にまで遡った太古の昔、天上で雷鳴が轟き、一本の丹塗矢が降ってきました。
矢が降ってから数日が経ったある日、賀茂川の上流で身を清めていた「玉依比売命(たまよりひめのみこと)(玉櫛媛、玉依姫とも)」は、川上から丹塗矢が流れてくるのを見つけます。不思議に思った玉依比売は丹塗矢を持ち帰り、丁重に床に祀りました。
その晩、眠っていた玉依比売は矢に込められた力によって懐妊し、一人の赤子を産みます。
赤子は「御子神(みこがみ)」と呼ばれるようになり、すくすくと成長。やがて元服(現代でいう成人)を迎えた際、玉依比売の父、つまりは御子神の祖父であり一族の長でもあった「賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)」が数多の神々を招いて七日七夜の祝宴を催します。
いまだに父の存在が不明な御子神に対し、賀茂建角身命は「父と思う神に盃をすすましめよ」と尋ねて盃を渡します。
すると御子神は、「我が父は天津神なり」と声高に言い放って盃を天上に向けて投げると、天井を突き破って雷鳴とともに天へ昇ってしまいます。「天津神」は日本神話における天上の世界「高天原」に住う神々のことであり、地上に住まう神よりもさらに高位の存在でした。
皆が呆気にとられる中、あまりに突然の別れとなって残された玉依比売は、息子の御子神に再び会いたいと願い続けます。そしてある夜、玉依比売の夢に御子神が顕れ、
「吾れに逢はんとは、天羽衣・天羽裳を造り、火を炬き鉾を捧げ、又走馬を餝り、奥山の賢木を採りて阿札に立て、種々の綵色を垂で、また葵楓の蔓を造り、厳しく餝りて吾をまたば来む」
とお告げを伝えます。
玉依比売はすぐにその神託に従って、神迎の祭を執り行いました。するとお告げの通り、立派な成人の姿となった御子神が神山に降臨したのです。
この御子神こそが上賀茂神社の祭神である「賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)」であり、玉依比売が執り仕切った賀茂別雷大神を迎えるための祭を行った場所が上賀茂神社の起源とされているのです。
ちなみに、玉依比売を懐妊させた丹塗矢の正体は、「火雷大神(ほのいかづちのおおかみ)」や「大山咋神(おおやまくいのかみ)」であるとされています。
斎王と上賀茂神社

創建後の上賀茂神社は、玉依比売命(玉櫛媛)の兄「賀茂玉依日古命(かもたまよりひこのみこと)」を祖とする賀茂一族の氏神を祀る神社として、「下鴨神」こと「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」とともに「賀茂神社(賀茂社)」と総称され、朝廷からの崇敬を受けることになります。
(ちなみに「下鴨神社」の祭神は、創建伝説のヒロインである「玉依比売命(玉櫛媛)」と、上賀茂神社の祭神「賀茂別雷大神」の祖父「賀茂建角身命」です。)
上賀茂神社は、延暦13年(794年)の平安遷都後には「皇城鎮護の神社」として一層の崇敬を受けることとなり、大同2年(807年)には神社における神階の最高位「正一位」を受けました。

さらに弘仁元年(810年)以降の約400年にわたっては、伊勢神宮の「斎宮」に倣った「斎院」が置かれ、皇女が「斎王」として奉仕した歴史も持ちます。
伊勢神宮の「斎宮」や「斎王」とは、伊勢神宮に天皇の代替わり毎に仕えた未婚の皇女のことです。選ばれた斎宮は、天照大神の「御杖代」と呼ばれる神の意を受ける依代して伊勢神宮に奉仕したのでした。
そんな伊勢神宮に倣った斎王が置かれたわけですから、日本で最も格式高い伊勢神宮に変わる神社、と捉えられていたことが窺い知れますよね!
近代〜現代の上賀茂神社

以降長きにわたって皇室からの崇敬を受け続けた上賀茂神社は、明治時代の近代社格制度においても伊勢神宮に次ぐ官幣大社の筆頭とされ、明治16年(1883年)には勅祭社に定められました。
1994年には「古都京都の文化財」の構成資産の一部として、ユネスコの世界遺産に登録された上賀茂神社。国家鎮護の寺社として、創建当初から現代に至るまで朝廷・天皇とは切っても切り離せない由緒ある神社なのです。
上賀茂神社の見どころ
それではここから、上賀茂神社へ観光したら絶対にハズせない見どころをご紹介していきます!
一の鳥居

上賀茂神社に到着して最初に出迎えてくれる鳥居が「一の鳥居」です! 境内への入り口に相応しい佇まいが美しいです。
「この鳥居をくぐった先が神域への道である」といわんばかりの真っ直ぐな参道も印象的ですね!
神馬舎

「神馬(しんめ)」は神さまが騎乗する馬として神聖視される馬のことで、神社に奉納されたり祭事の際に登場したりという役割を担います。
また、神馬の種類は白馬であることが多く、ここ上賀茂神社の神馬「神山号(こうやまごう)」も白馬です。
神山号は基本、日曜祝日と大きいお祭りのある9:30~15:00に出舎しており、ニンジンをあげることはもちろん、「神馬お守り」や「神馬みくじ」といったこのときにしか手に入らないお守りやおみくじが授与されています。うまく時間を合わせてぜひ神山号とご対面してみてくださいね!
細殿と立砂

二の鳥居をくぐり社殿が並ぶ境内中心部に入ると、正面に見えるのが「細殿(ほそどの)」と「立砂(たてすな)」になります! これこそが上賀茂神社のシンボルとも言える最大の見どころです!
「細殿」は天皇や斎王が上賀茂神社に参拝する際に装束を整えたとされる場所で、控えめながらも美しい外観が非常に印象的。
そして細殿の前に整えられた「立砂」は、祭神である賀茂別雷大神が玉依比売命の儀式に応えて雷鳴とともに降臨したとされる「神山」をかたどったもので、つまりは”祭神の依代”となっています。

左右で対に立っているのは陰陽道に基づくものだそうで、立砂の先端にある松の葉は、賀茂別雷大神が神山に降り立ったときに頂上に特別な松の木が立っていたと言われることから。賀茂別雷大神はこの松の葉を目印にして降臨するとされています。
また、上賀茂神社の立砂は清めの塩や盛り塩のルーツになったとも言われています。まさに、正真正銘のパワースポットというわけですね!
楼門

細殿、授与所、手水舎を過ぎると、本殿と権殿に通じる門「楼門」が現れます。
境内そのものはこぢんまりとしている上賀茂神社においては大きな建造物であり、美しい朱塗と相まって強い存在感を放っています。
中門と本殿・祭神とご利益

楼門の先にある門が「中門」です。本殿に直接入ることはできないので、この中門から御祭神の賀茂別雷大神へとお参りを行います。
また、祈祷殿の横に巨大な矢が刺さっている時があります。これは祝い事や祭りの際にのみ置かれるもので、創建伝説において玉依比売命が川から持ち帰ったという「丹塗矢」をかたどったものになっています。
言われてみれば上賀茂神社の伝説、桃太郎に似たお話の始まりな気がします。まさか、桃太郎もこの上賀茂神社に関わっていたりして…。
ご祭神とご利益

【祭神】
賀茂別雷大神
【ご利益】
厄除け・方除け・開運・八方除け・雷除け・災難除け・必勝・電気産業守護・旅行安全
片岡社

楼門のすぐ近くに「片岡社」こと「片山御子神社」という社があります。
この片岡社には、上賀茂神社が創建されるきっかけとなった人物「玉依比売命」が祀られています。玉依比売は上賀茂神社の祭神である賀茂別雷大神の母であり、同時に「女性守護の女神」ともされており、「縁結びの神様」としての信仰もあるのです。
この御利益には、なんと『源氏物語』の作者である「紫式部」もあやかりに来たとか…! 実際、紫式部が残したとされる和歌もあるのですよ!
ほととぎす 声待つほどは 片岡の 森の雫に 立ちや濡れまし
(ほととぎすの声が聞こえるまで、片山の森の雫に濡れながら待っていようかな)
京都最古のパワースポットに深く関わる女性守護の女神様ですから、まさに由緒正しき縁結びの社といえます! ぜひご利益にあやかりましょう!
八咫烏おみくじ

上賀茂神社の名物といえば、「八咫烏おみくじ」を忘れてはいけません!
八咫烏の中におみくじが入っているユニークなおみくじで、八咫烏はそのまま持ち帰ることができます。置物として日々の生活を見守ってくれるわけですね!(デスクに置く方が多いと言い、筆者も長く仕事場のデスクにおいています!)
ちなみに、「八咫烏」とは日本神話に登場する三本足のカラスのこと。初代天皇「神武天皇」の東征の際に熊野国から大和国への道案内をし、神武天皇を無事導いたとされています。
この八咫烏、実は玉依比売の父であり賀茂氏の始祖である「賀茂建角身命」の別姿とも言われているのです。賀茂建角身命は下鴨神社(賀茂御祖神社)に祀られているのですが、賀茂神社の中心である上賀茂神社にもその名残があるというわけですね!
渉渓園とならの小川

境内の南東が小さな林のようになっている上賀茂神社。ここは「渉渓園(しょうけいえん)」と呼ばれる庭園で、平安時代には、歌人たちが庭園を流れる「ならの小川」に杯を流しながら和歌を詠む「賀茂曲水宴」などの祭事が行われていたといいます。
実際に百人一首にも詠まれている場所ですから、その穏やかなせせらぎは平安当時から愛されていたのですね!
また、ならの小川は古くから禊の場としても知られています。神様に仕える斎王が住まう場所ですから、それだけ清らかな場所であったのも間違いなさそう。
渉渓園とならの小川の近くには三の鳥居もあるので、ここから境内を抜けていくのもよいかもしれませんね!
桜の名所としての上賀茂神社

パワースポットとして知られる上賀茂神社ですが、実は春の桜の名所としても非常に人気があります。
その代表が、一の鳥居から二の鳥居までの参道横にある樹齢150年の「斎王桜(紅八重枝垂れ桜)」と白い花が咲き誇る「御所桜」です!
天皇や朝廷との関わりと伝統を表現する桜は、まさに斎王の美しくも上品な佇まいを彷彿させる見事な枝垂れ桜となっていますよ!
👉 京都の桜の名所を知りたい方はコチラも要チェック!見どころをまとめました
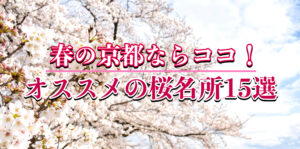
式年遷宮


ここで、上賀茂神社特有の催し物として「式年遷宮」をご紹介します。上賀茂神社へ行く際に知っておくとより深く観光を楽しむことができますよ!
「式年遷宮」とは、20年に一度、境内自体はそのままに社殿や神宝をはじめとする境内の”中身”すべてを一新し、ご祭神に新しく清浄な境内や社殿へと遷ってもらうための儀式のことです。もともと式年遷宮を行っている伊勢神宮では「20年に一度」ですが、上賀茂神社・下鴨神社の賀茂神社では「21年に一度」行われているのが特徴です。
上賀茂神社(賀茂神社)における式年遷宮は奈良時代から始まったとされており、平成27年(2015年)に第42回の式年遷宮が行われました。


江戸時代までは式年遷宮のたびに社殿を造り替えていましたそうですが、現在は社殿の多くが国宝や重要文化財に指定されているため、主に社殿の檜皮葺屋根の修復を行うことで遷宮としています。
ともあれ、この式年遷宮のおかげで、境内がその地にあり続けながら創建当初の姿に限りになく近い形で今なお現存することが可能になっていると言われています。上賀茂神社が京都最古であっても創建当時の土地に建ち続け、パワースポットたり得る理由の一つなのですね!


上賀茂神社の社祭「葵祭」
上賀茂神社最大の見どころと言われるのが、京都三大祭りにも数えられる「葵祭」になります。
かつては「賀茂祭」と呼ばれていた葵祭は平安時代から続くお祭りで、これは日本でも最古の部類に入ります。また、上賀茂神社が正一位に据えられた大同2年(807年)には勅祭とされた歴史も持ちます。
葵祭(賀茂祭)の起源


葵祭(賀茂祭)の起源は、玉依比売命(玉櫛媛)が息子である賀茂別雷大神を迎えるために行った祭りであるとされています。
この祭りで玉依比売は、夢の中で「葵楓の蔓を装って祭をせよ」と賀茂別雷大神からお告げを受けたことで葵を用います。これがきっかけで、賀茂祭においても社殿に葵を飾り、祭の奉仕者が葵を身に付けるようになったみたいですね!
そしてこのエピソードから、「賀茂祭」は「葵祭」とも呼ばれるようになったといわれています。
上賀茂神社と葵の関係


上賀茂神社では葵が重要な植物として扱われています。
それは当然、玉依比売と賀茂別雷大神の神話と葵祭によるもの、そして、北東の杜に二葉葵が群生していることが理由だと考えられがちなのですが、実は「葵」という言葉そのものにも重要な意味があるのです。
「葵」という言葉は、古くは「あふひ」と読み、「ひ」は「神霊」を意味していました。つまり、「葵」とは「神と逢うこと」や「神と逢う日」を指す言葉でもあったのです。
この言葉の意味も相まって、葵は上賀茂神社の神紋として扱われると同時に大切に守られてきたと考えられているのですよ!
葵祭の見どころと歴史


そんな上賀茂神社にとって重要な「葵」を冠する葵祭最大の見どころは、色とりどりの平安装束で装った人々が行列をつくって練り歩く「路頭の儀(ろとうのぎ)」ですね! 京都御所から下鴨神社(賀茂御祖神社)を経て上賀茂神社(賀茂別雷神社)に至る道のりは、全行程で約8kmにも及びます。
もともとは、玉依比売が息子である賀茂別雷大神を再びこの現世に迎えるために催した祭を模していた葵祭。弘仁元年(810年)に上賀茂神社に斎院がおかれるようになると、斎王が葵祭に祀られ祭りに奉仕するようになります。
ここから建暦2年(1212年)に斎院制度が終わるまでは、斎王が路頭の儀における中心的な役割・存在を担うこととなります。(現在の葵祭では、斎王に代わる「斎王代」がその役目を果たしていますよ!)


そんな葵祭、平安時代の頃は上賀茂神社境内における祭儀は一般の人々にはほとんど公開されておらず、御所から上賀茂神社への行装のみ見ることができたそうです。ですので、皇族や貴族たちは牛車を並べたり檜皮葺の桟敷を設け、一般の人々は京の住民のみならず地方から上京してきた人々もつめかけ、街は大きな賑わいを見せていたと伝えられています。
この様子は、『源氏物語』をはじめとする平安時代に書かれた日記や物語などの書物にも記されているほどなのですよ!


平安時代には栄えた葵祭でしたが、室町時代中頃から衰退してしまい、応仁の乱以降は京都の町の混乱とともに完全に廃れてしまいます。
その後約200年の時を経て、江戸時代の元禄7年(1694)に上賀茂・下鴨両神社、朝廷・公家、幕府の協力によって祭が再興され、明治時代に入るまで執り行われました。そして明治時代初期に一時期の中断を経て、明治17年(1884年)に明治天皇によって、春日大社の春日祭と石清水八幡宮の石清水祭と共に「日本三勅祭」の一つとして三度祭儀が再開されることとなりました。
毎年5月15日に行われる「葵祭」こと「賀茂祭」。みなさんもぜひ足を運んでみてくださいね!


上賀茂神社の拝観情報・アクセスなど


拝観時間
5:30~17:00(祭典等により変更有り)
【楼門・授与所】
8:00〜16:45
【国宝本殿の特別参拝】
10:00〜16:00(土日・祝祭日は〜16:15)
拝観料
境内自由散策のため無料
【国宝本殿の特別参拝】
初穂料:大人500円(中学生以下は無料)
※夏期(7月上旬~中旬)は大人800円、小学生400円
※秋期(10月中旬〜12月上旬)は大人1,000円、小中学生500円
桜の見頃


4月上旬~4月中旬
アクセス・駐車場
〒603-8047
京都府京都市北区上賀茂本山339
TEL:075-781-0011
【電車・バスの場合】
・地下鉄烏丸線「北山駅」から徒歩約15分
・市バス4・46・67番系統「上賀茂神社前」で下車後すぐ
・市バス9・37・北3番系統「上賀茂御薗橋」で下車後、徒歩3分
・京都バス30・32・34・35・36番系統系統 「上賀茂神社前」で下車後すぐ
【車の場合】
・JR京都駅から車で約30分
・地下鉄烏丸駅から車で約20分
【駐車場】
6:00〜22:00(出庫は24時間可能)
※30分ごと100円(繁忙期は1回500円となる)
👉 京都中心部でオシャレかつ便利なホテルをお探しならコチラも要チェック!


上賀茂神社の観光地紹介 まとめ


ということで今回は、「上賀茂神社」こと「賀茂別雷神社」についてご紹介してきました!
京都でも屈指の歴史を持ち、最古のパワースポットとも言われる上賀茂神社。ご利益によるパワースポットではなく、神話や成り立ちからそう言われる”ガチ”のパワースポットなのが、葵祭を除いた上賀茂神社最大の魅力にして見どころと言えるでしょう。
実は筆者自身も、初めて上賀茂神社に足を運んだ際に言葉ではうまく表現できない不思議で清らかな雰囲気を感じ、それ以降京都へ行ったらほぼ毎回足を運んでいる神社になります。
京都のみならず日本全国を見渡してもトップレベルのパワースポットである上賀茂神社。世界遺産にも登録されている歴史あるこの地へ、あなたもぜひ足を運んでみてくださいね!


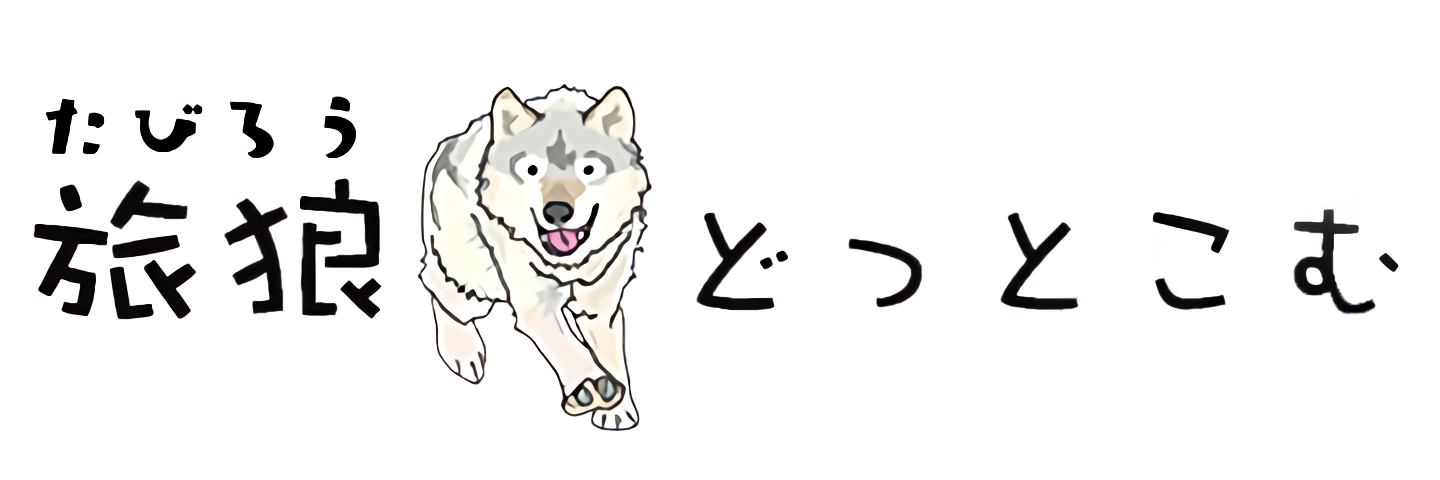


この記事へのコメントはこちらから!
コメント一覧 (9件)
[…] 👉 上賀茂神社について詳しくみてみる […]
[…] →上賀茂神社について詳しく見てみる […]
[…] ってなかったところに行く」ということで、この日はずっと行きたかった「苔寺」こと「西芳寺」からスタート! 昨日の上賀茂神社と今日の苔寺が、今回の一人旅のメインの目的です。 […]
[…] ってなかったところに行く」ということで、この日はずっと行きたかった「苔寺」こと「西芳寺」からスタート! 昨日の上賀茂神社と今日の苔寺が、今回の一人旅のメインの目的です。 […]
[…] くお願いいたします。。 関連記事上賀茂神社について、さらに詳しく知りたい方はコチラの記事をどうぞ!👉 旅狼史上No.1のパワースポットです。 あわせて読みたい 【京都観光 […]
[…] 関連記事京都最古の最強パワースポット!上賀茂神社の見どころ・歴史・神話👉 上賀茂神社について詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください あわせて読みたい 【京都 […]
[…] 詳しくはコチラ!京都最古パワースポットで不思議体験? 世界遺産「上賀茂神社」の魅力とは?👉 上賀茂神社について詳しくみてみる あわせて読みたい 【京都観光】最古 […]
[…] 長らく、同じく創建に玉依姫命が関わっている「賀茂別雷神社(上賀茂神社)」の摂社とされてきましたが、明治以降になって独立した神社となりました。そのため、江戸時代までは上 […]
[…] 👉 上賀茂神社について詳しくみる […]