みなさんこんにちは! 観光情報サイト「旅狼どっとこむ」の旅狼かいとです!
今回は「関東No.1パワースポット」との呼び声も高い秩父の「三峯神社」についてご紹介します!
「怖いくらい人生が変わる」「呼ばれる気がする」「ヤバすぎて人を選ぶ」とまで言われる三峯神社は標高1100mに鎮座する神社で、全国的にみても珍しい狼信仰でも知られています。さらには、ヤマトタケルやイザナギ・イザナミに関わる伝説も数多く残っており、山がちな立地だからこそ見られる四季折々の風景も楽しむことが出来ちゃうのです!
そんな三峯神社のパワースポットとしてのご利益や白いお守り「氣守」についてはもちろん、歴史や見どころ、便利なアクセス情報まで、旅行前に知っておくとさらに三峯神社観光が楽しくなること間違いなしの情報をお届けします!
三峯神社の歴史
まずは三峯神社の歴史をご紹介します! ご利益や見どころをより楽しむために、意外と重要な要素だったりしますよ!
ヤマトタケルの創建伝説

三峯神社を創建したのは、かの有名な古代日本の大英雄「日本武尊(ヤマトタケルノミコト)」であると伝説では伝えらています。
日本武尊(以下ヤマトタケル)は景行天皇の子であると伝えられる日本の伝説上の人物で、九州の熊襲建兄弟を討伐した西征や、草那藝剣を用いて東方の蛮族を討伐し各地の神々を平定してまわった東征の伝説など知られています。
そんなヤマトタケルが現在の三峯神社がある山に登って、日本神話における『国産み』の伝説と『神産み』の伝説で知られる「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」と「伊弉册尊(いざなみのみこと)」を祀って創建した神社こそ、「三峯神社」なのです。
※『国産み』は「天沼矛」を使って「日本」という島を創造したとされる伝説で、『神産み』はイザナギとイザナミが男女の営みによって神々を産み落とした伝説です。
名前の由来とヤマトタケル

「三峯」という名前は、社地が白岩山・妙法ヶ岳・雲取山の三山に囲まれていることから景行天皇が授けたと伝えられています。この由来は、ヤマトタケルと父である景行天皇の関係が良い『日本書紀』に基づいたものとされています。
というのも、『古事記』では父である景行天皇はヤマトタケルをあまり好いていなかったと描かれているからです。ヤマトタケルが日本各地を平定していった武勇も、息子の荒々しい性格と強大な力におそれを抱いていた景行天皇が、ヤマトタケルをできるだけ遠くへ置いておくための口述と言われていますからね。
そんな父からの扱いに勘づいていながら、ヤマトタケルは父に認められるために各地へ奔走したと記されています。まともな兵も与えられないままの遠征で、最後には不運が重なって死期を早めてしまったヤマトタケル。今では「悲劇の英雄」としても語られています。
※『古事記』では白い大猪、『日本書紀』では大蛇と記されている「伊吹山の荒ぶる神」と対峙した際に神に対するタブーを犯してしまい、それがきっかけでヤマトタケルは命を落とすことになってしまいます。
中世以降の三峯神社

文武天皇の時代になり、修験の祖と謳われる「役小角(えんのおづぬ)」が伊豆から三峯山に往来して修行したと伝えられています。この頃から、三峯神社で修験道が始まったと考えられています。
さらに淳和天皇の時代には、勅命によって弘法大師(空海)が十一面観音の像を刻み、社殿の脇に本堂を建て本地堂としたとも伝えられています。
その後の中世以降は、関東を拠点とする武将たちを中心に崇拝を受けて大いに栄えた三峯神社。しかし1300年中頃、足利氏を討つために挙兵しのちに敗れた新田義興・義宗らがこの山に身を潜めたことより、足利幕府が成立後に社領が奪われ、一度は衰退してしまいます。

それでも1500年初頭、修験者の「月観道満」が廃れた三峯神社を知り、再興させることに成功。以後、聖護院派天台修験の関東総本山とされて再び栄えていきました。
月観道満が神社を再興して以来、歴代の山主は花山院家の養子となって寺の僧正になることが通例となったため、寺の定紋に花山院家の紋所である「菖蒲菱」が使われるようになったと言われています。
三峯神社と狼信仰

三峯神社を語る上で忘れてはいけないのが、「御眷属信仰」や「三峯講」とも呼ばれる「狼信仰」ですね!
社伝においては、神社を創建したヤマトタケルを三峰の地に道案内したのが山犬(狼)であったとされ、このことから神様の使いとして一緒に祀られたとされています。
一方、三峯神社における狼信仰そのものは江戸時代からはじまったとされています。
当時、オオカミは農作物を荒らすイノシシなどを餌とする動物であり、人間にとっては「害獣を駆除してくれる存在」だったといいます。
そのため秩父に住む人々は、山中に生息していた狼を猪などから農作物を守る「神の眷族」ないしは「神使」と考えていたといわれています。そしていつしか、狼たちを「お犬さま」として崇めるようになったことが、狼信仰発展のきっかけと考えられているそうです。
さらにその後、「狼は盗戝や災難からも守ってくれる神さまである」と解釈が転じていき、現在では秩父を代表するこの三峯神社が、日本有数の狼信仰が篤い神社として知られるようになったのです。

ちなみに、狼の語源は「大神」だとする説があるくらい、日本では古くから狼信仰が存在しているのですよ! 三峯神社のみならず日本各地に狼を信仰する寺社仏閣が建ち、神話や物語にも登場することがその証明と言えるでしょう。
ジブリ映画『もののけ姫』のモロの君も「お犬さま」だとされていますから、古来より狼が日本人の信仰対象として根付いているのでしょうね!
三峯神社は本当に人を選ぶの?

三峯神社はよく、「人を選ぶ」だったり「厳しい」だったりと言われます。
実際に足を運んでみると、確かに澄んだ空気や美しい社伝、素晴らしい三峰の自然の風景を感じることができましたが、別段僕には変わったことはありませんでした。
とはいえ、霧が立ち込めている時の三峯神社は本当に異世界のような雰囲気だと言われていますし、このような山奥に立つ神社ですから、何か特別な力があると信じられるのはわかる気がしました。
また、神社と人間には「相性」があるとされていますから、「自分が三峯神社に選ばれているのか」を知るには、実際に足を運んでみてどう感じるかが一番だと思いますね!
神社との相性なんて本当にあるの?

ちなみに、「こんな神社との相性なんてものオカルトじみているよ〜」と僕も昔は思っていたいのですが、京都の上賀茂神社へ行ってから考えを改めるようになりました。パワースポットって本当にあるんだ、と体感すると、信じていないあなたもわかると思います。
そのきっかけの一つに三峯神社がなる可能性は大いにありますからね! 気になる方は、この後の見どころ等も参考にしてぜひ三峯神社に足を運んでみてください!

三峯神社の見どころ
それではここから、三峯神社に行ったら絶対に見逃せない観光スポットをご紹介していきます!
白の三ツ鳥居

三峯神社に到着して最初に出迎えてくれるのが、「白の三ツ鳥居」と呼ばれる鳥居になります。
神社にあるいわゆる”普通の鳥居”である明神型鳥居が3つ組み合わさっており、しかも色が赤ではなく”白”なのです! 形と色と二つの意味で非常に珍しい形態の鳥居であり、三峯神社のシンボルとなっています。
そして鳥居の左右には、狛犬ではなく狼が鎮座していますね!

こうして境内のいたるところで、お犬様こと狼たちが参拝者を見守ってくれていますよ!
随身門

鳥居をくぐり参道を進んでいくと、次に現れるのが「随身門(ずいしんもん)」になります。
元禄4年(1691年)に建立されて以来数回の再建を経て、平成16年(2004年)の漆の塗り替えによって現在の姿となりました。
想像以上に大きな山門は重々しい重厚感を与えてくるような雰囲気で、「ここからは神の領域である」と言わんとばかりの存在感でした。
拝殿

境内に足を踏み入れると真っ先に目に入るのが、階段を登った先にたたずむ「拝殿」です! 現在の姿は、平成16年(2004年)に漆の塗り替えが行われたものになります。
そんな拝殿の見どころは、なんといってもその豪華絢爛な装飾でしょう!
向拝中央の透かし彫りには、上部に中国故事の「司馬温公の瓶割り」が、下部には七福神による「琴棋書画」 が表現されており、他にも龍や獅子、鳳凰に鶴など、縁起がよいとされる者たちで溢れかえっています…!

特に言及されていないのですが、装飾は日光東照宮を彷彿とされるものもあります。麓の秩父神社は徳川家康の命によって社殿が整備されていますから、何らかの関係があるのかもしれません。
ともあれ、見ているだけでなんだか力が湧いている、テンションが高まってくるところでしたよ!

【司馬温公の瓶割り】
司馬温公は司馬光という北宋の政治家を指します。
温公は子供の頃、大きな水瓶に誤って落ちてしまった友達を助けるために、とても貴重とされたその瓶を石で割ってしまいます。大切な瓶を割ったので叱られることを覚悟した温公でしたが、むしろ父親は温公を褒め、「どんなに貴重なものであっても、人の命には変えられない」という命の大切さを教えたと言います。
【琴棋書画】
「琴を弾いて囲碁を打ち、書を書いて絵を描く」こと。中国においては「四芸」と呼ばれ、教養ある文人の嗜みとされました。日本でも室町時代以降において、屏風絵や工芸品の図柄などのモチーフとして多く用いられています。
龍が浮かび上がってくる石畳

拝殿の左手側へと進むと、ちょっと変わった石畳があります。それが「水をかけると龍の模様が浮かび上がる」という石畳です!
平成24年(2012年)の辰年に突如あらわれたといわれており、「偶然にしては…! 」と一時話題となった新たなパワースポットなのです。
たしかに、龍の長い鼻先と赤い両目、そして角のようなものと小さな体が浮かび上がっているように見えますよね!
御神木(重忠杉)

拝殿を護るかの如く両脇に高くそびえる巨大な杉の木こそが、三峯神社における「御神木」になります。
樹齢800年ともいわれるこの御神木は、鎌倉時代の武将「畠山重忠」が奉献したと伝えられており、そこから「重忠杉」とも呼ばれています。

近くの立て札には「神木より発する『氣』は活力そのもの」と書かれており、御神木に宿る”氣“をここで授かり、三峯神社名物の「氣お守り」に宿すことができるのです!
「氣」の授かり方はとても簡単。3度深呼吸をしてから願い事を唱えるだけですから、拝殿と一緒に必ずお参りしたい三峯神社のスピリチュアルスポットです!
本殿

拝殿の裏に隠れるように立つ「本殿」を見るには、拝殿の右側(龍の石畳とは反対方向)から覗き込む必要があります。意外と見落としがちだと思いますので気をつけてください。御神体が据えられ、神社の主神を祀っているのは拝殿ではなく「本殿」ですからね!
現在の本殿は寛文元年(1661年)に建立されたもので、一間社春日造という日本の伝統的な神社建築様式が採用されているのが特徴です。
そんな本殿に祀られている三峯神社の主祭神は、歴史の創建伝説でもご紹介したように「伊邪那岐」と「伊邪那美」ですよ!
縁結びの木

拝殿を見て境内を左の方へと進み、社務所・小教院・興雲閣を通り過ぎてさらに進んでいくと見えるのが、「縁結びの木」になります!
「山の斜面に寄り添って立つ二本の木がまるで夫婦のようだ」と言われるようになったことから、いつからかここが縁結びのパワースポットとして知られるようになったそう。
御神木の前に設置された拝殿にはマンガタッチの巨大絵馬が掲げられていますから、すぐにわかると思いますよ!(多分イザナギとイザナミですね笑)

三峯流縁結びの作法は「えんむすびこより」と呼ばれています。
自分の名前と縁を結びたい人の名前をそれぞれ書き、それをより合わせて紐状の紙縒にして納めることで恋愛成就がなされると言われていますよ!
お仮屋(遠宮)

縁結びの木からさらに奥へと進んでいくと、三峯神社の眷属である「お犬様」の住まい「お仮屋(遠宮)」があります。
眷属であるお犬様は、普段は三峰山の深い山中に身をひそめているとされています。ですのでこのお社を「仮のお宮」、つまり「お仮屋」として祀っているのです。

つくりはシンプルなお社ですが、近くにはいたるところに像となった狼たちがいます。狼好きからしたら色々な意味でたまらない名スポットですね…!
祖霊社

再び拝殿の方へ戻り、今度は拝殿に向かって右側にある見どころを見てみましょう。
本殿に向かって右側に立つ朱塗りのお社は、「祖霊社(それいしゃ)」と呼ばれています。三峰山が開山して以来この地に住まわれてきたすべての祖霊を祀っているという、「冷静に考えたら結構すごいお社なんじゃないか?」と個人的には感じる場所。
春と秋のそれぞれのお彼岸と8月15日の年に3回、祭りも催されます。
国常立神社

祖霊社の隣に立つのが「国常立神社(くにとこたちじんじゃ)」になります。
ここにはその名の通り、「国常立尊(くにとこたちのみこと)」が奉られているのですが、この国常立尊、一体どんな神様かご存知ですか?
実はこの国常立尊こそが、『日本書紀』において天地開闢の際に最初に現れた”始まりの神様”なのです!
冷静に考えたらとんでもない神様なのですが、どういうわけかあまり多くを語られておらず、それゆえに祀っている神社もそれほど多くないというのが実情。ここ三峯神社でも、このような小さな祠でひっそりと信仰されています。
国常立尊にまつわるうんちく

ちなみに、『日本書紀』における国常立尊は「陽気のみを受けて生まれた神で、全く陰気を受けない純粋な男性」という「純男の神」として描かれていますが、『古事記』では五柱の別天津神の後に顕現した「神世七代」の中で最初に現れた神、つまり6番目に現れた神とされています。また、男女の概念がない独神であり、姿を現さなかったともされています。
実は三峯神社には、配祀神として『古事記』において最初に顕現した「天之御中主神」が祀られています。ですので、国常立尊は天之御中主神と同一視されたことで、この地に祀られたのではないでしょうか。
これは僕個人の考察であり特に証拠があるわけではないのですが、こう考えるとあまりこのお社について言及されていない理由も頷けますからね! みなさんはどう思いますか…?
摂末社

国常立神社の先に目を向けると、ズラっと小さなお社が並んでいます。
ここは「摂末社(せつまっしゃ)」と呼ばれる場所で、境内の中に小さい神社があるという不思議な空間となっています。
小神社は全部で23社あり、月夜見命を祀る月讀神社や宇迦御靈命を祀る稲荷神社、諏訪神社に春日神社などなど、非常によく知られている神社が多いのも特徴です!
いずれも三峯神社にゆかりの深い神様が祀られていると言われていますから、この光景と合わせて考えると、関東No.1パワースポットという異名も伊達ではないと感じますよね!
神楽殿

拝殿の近くにたたずむ木造の殿舎は、その名の通り神楽を行うための「神楽殿」です。
そもそも「神楽」というのは、祭りに際して神々への感謝や祈りを奉納するために奏される歌舞であり、そこから、巫女などが人々の穢れを祓うために舞う、といった意味合いも含まれるようになったといいます。
神楽には大きく分けて二種類あり、宮中で行われる特別な神楽である「御神楽」と、一般的な”神楽”を意味する「里神楽」が存在します。
三峯神社における神楽は里神楽の中でも「太々神楽」と呼ばれるもので、いわゆる”お神楽衣装”を身に纏い、面をかぶって笛太鼓に合わせて日本の神話をもとにした舞を踊る舞劇だったそう。
そんな「三峯神代神楽」と名付けられた三峯神社の神楽は毎年4月に奉納されていましたが、後継者不足によって継承が困難となり、2015年をもってその長い歴史に幕を下ろすことになってしまったのです。
同じく秩父のパワースポットとして知られる秩父神社の「神代神楽」は、秩父夜祭と共にユネスコの無形文化遺産に登録されていますから、いつの日か三峯神代神楽がまた見られる日が来るとよいですね。。
遥拝殿

ここから一気に、場所が随身門付近まで戻ります!
随身門の向かい側の階段を登ると、「遥拝殿(ようはいでん)」という場所があります。妙法ヶ岳山頂に鎮座する三峯神社の「奥宮(おくのみや)」が見えるため、古くはここから眺め拝んでいたといいます。
また、三峯神社の境内では唯一下界を見ることができる場所でもあり、その絶景は今なお健在! 秩父の山間の素晴らしい風景を楽しむことができますよ!

日本武尊銅像

白の三ツ鳥居から境内の方へと進んでいくと、左に随身門への参道、右に遥拝殿と分かれるのですが、そこを曲がらずにまっすぐ進むと「日本武尊(ヤマトタケルノミコト)」の銅像を見ることができます。
歴史のところでお話ししたように、三峯神社を創建したとされるのがこのヤマトタケルですからね! このような像が立っていることも頷けます。
ちなみにヤマトタケルは、三峯神社や秩父神社と共に「秩父三社」に数えられるパワースポット「宝登山神社」の創建伝説にも登場します。
宝登山神社創建の伝説にも山犬とヤマトタケルの関係が描かれているため、秩父において狼とヤマトタケルは切っても切り離せない関係と言えそう。これもまた、関東一のパワースポットたる所以なのかもしれませんね!
三峯神社奥宮

見どころ紹介の締めを務めるのが、三峯神社の「奥宮(おくのみや)」です!
三峯神社の奥宮は妙法ヶ岳の山頂に位置しており、そこまでは片道約2.5km、徒歩にして約1時間半の山登りとなります。ですので奥宮への参拝ばかりは、みんながみんなにはオススメしません。。
しかし!
奥の院や奥社とも呼ばれるこの「奥宮」こそが、本来神様がいらっしゃる聖域。時間に余裕がある方はぜひ、妙法ヶ岳の山頂1,332mを目指してみてください!
澄み渡った空気は本当に素晴らしく、奥宮についたときの達成感はひとしお! そして何といっても、”やはりこの山道と奥宮こそが真のパワースポットなんだな”と感じさせてくれましたよ!

ちなみに、毎年5月3日に山開きの祭事が、10月9日に山閉の祭事が行われますが、山閉の後でも登山は可能となりますのでご安心を。11月には雲海を見ることもできるそうですからね!
ただし、道は結構険しく、後半からは「これ普通に落ちるよね?」みたいな道も進むので、雨の日や霧が出ている日、冬の雪が積もっている日は軽い気持ちで登ると本当に危険だと感じました(入り口では登山届を書き入れるところがあるくらいです)。
筆者のような”あくまで旅行者として”という方は、どうか天気に気をつけて登山をするか検討してください。


三峯神社の白いお守り

三峯神社といえば「白い氣守」でとても有名です。
「白」には「清浄」や「太陽」を表す意味があるほか、ヤマトタケルを三峰の地に導いたのが白い狼だったことから、白色のお守りなのだそうですよ! また、白は何色にでも染まる色であることから「新しいスタート」という意味もあり、このことから毎月の一日に頒布していたそう。
そんな「白い氣守」ですが、残念ながら現在は配布されていません。
というのも、2013年の7月から毎月1日にのみ授与された白い氣守は、三峯神社のパワースポット人気と相まってとんでもない人気を博し、最盛期には、普通なら1時間ほどで行けるところから6時間経っても着かないほどの大渋滞となっていたようです。これが地元の方々の生活にまで大きな影響を与えてしまったことから、2018年から授与を中止しているのです。

現時点では再開の見込みは立っていないとのことですから、白い氣守はもはや幻のお守りと言えるかもしれません。
とはいえ、普通の「氣守」は通常通り授与されていますから、ぜひ氣守に御神木の氣を集め、三峯神社の霊験をいただいてくださいね!
三峯神社の祭神とご利益


続いて、三峯神社の祭神とご利益についてご紹介します!
主祭神
【伊邪那岐神(イザナギ)・伊邪那美命(イザナミ)】
「日本」という島を創造した『国産み』と、その後神々を産み落とした『神産み』の伝説で知られる二神。
配祀神


【天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)】
『古事記』において、天地開闢の際に最初に登場する「始まりの神」。
【高御産巣日神(たかみむすびのかみ)】
『古事記』において、天之御中主神についで出現した「天の生産」と「創造」を神格化した神。性別のない独神だが男女の”むすび”の「男」の象徴とされる。
【神産巣日神(かみむすびのかみ)】
『古事記』において、高御産巣日神についで出現した「地の生産」と「創造」を神格化した神。性別のない独神だが男女の”むすび”の「女」の象徴とされる。
※日本神話において天地開闢に関わる天之御中主神・高御産巣日神・神産巣日神の三神を「造化三神」と呼ぶ。
【天照大神(アマテラス)】
イザナギを追いかけて黄泉の国から帰還したイザナギが、黄泉の穢れを落とした際に左目から生まれた神。高天原を統べる、日本神話における主神にして太陽神。
もともとは男神であり、推古天皇や持統天皇、元明天皇といった女帝の姿が反映されたものという説もある。
※同じくイザナギの右目から生まれた月神「月読命(ツクヨミ)」とイザナギの鼻から生まれた「須佐之男命(スサノオ)」と合わせ、「三貴子(みはしらのうずのみこ、さんきし)」と呼ばれる。
ご利益


神社ではよく聞く「ご利益」ですが、三峯神社ではそういったことはあまり語れれない気がします。
というのも、御神木の「氣」こそが、自然信仰の形としての三峯神社最大の御利益であり霊験であり、「この三峯神社と三峰山こそがパワースポットそのもの」と考えることが、もっともしっくりとくる考え方だからです。
そういった意味では、「神社に足を運ぶ」ということで既にお力はいただいているように感じます!


とはいえ、三峯神社にもご祈祷や神事は存在します。中でも三峯神社特有なのが、「御眷属拝借」と「ごもっとも神事」ですね!
御眷属拝借


「御眷属拝借」とは、御眷属と呼ばれる「狼」の力を御神札として1年間拝借し、地域や一家のご守護を祈る祈願のことです。
古くから続くこの御眷属拝借こそが三峯神社での狼信仰の形とされており、狼は火や見たことのない人間を見ると吠えることから、火難盗難除けや諸難除けの霊験を授けてくれるとされています。
ごもっとも神事


「ごもっとも神事」とは、節分に行われる三峯神社独自の神事です。
裃姿の年男が三方にのせた福枡の豆を「福は内、鬼は外」と唱えながらまいていき、後ろの添人が大声で「ごもっともさま」と叫びつつ巨大な”ごもっとも様”を前上方に突き出します。
この「ごもっとも様」は、1mほどの檜の棒の頭に注連縄をまき根もとに蜜柑二つを麻縄でくくった陰茎を象徴するもので、五穀豊穣、夫婦和合、子宝、家内安全、悪霊退散のご利益を授けてくれるとされています。
三峯神社の観光地情報


最後に、三峯神社の拝観時間や拝観料、アクセスや駐車場についての情報です。
拝観時間
境内自由参拝
・授与所:9:00〜17:00
・祈願受付:9:00〜16:00
拝観料
境内自由散策のため無料
紅葉の見頃
10月下旬〜11月上旬
三峯神社へのアクセス


〒369-1902
埼玉県秩父市三峰298-1
TEL:0494-55-0241
【電車とバスの場合】
・「西武秩父駅」から西武観光バス「三峯神社線」で約75分
・秩父鉄道「三峯口駅」から西武観光バス「三峯神社線」で約50分
【車の場合】
・関越自動車道「花園IC」から国道140号線、皆野寄居バイパスを経由する(東京方面から)
・中央自動車道「甲府昭和IC」から国道140号線、雁坂トンネルを経由する(山梨方面から)
駐車場
秩父市営の三峰駐車場を利用する
【利用時間】
通常時は8:00〜18:00
【料金】
・普通車:520円
・二輪車:210円
三峯神社 まとめ


ということで今回は、秩父の三峯神社についてご紹介してきました!
「呼ばれる」「人を選ぶ」という噂や「関東No.1パワースポット」という評判も伊達ではない歴史や由来、見どころやご利益があることがわかりましたね!
三峯神社周辺や奥宮への山登りでは秩父の大自然を感じることができますし、境内の雰囲気もとても澄みきった素晴らしいものがありました。
電車やバスであっても、都心から日帰りで旅行することが可能ですから、ぜひ最近何かに行き詰まっている方や気分転換をしたいという方は、三峯神社へ足を運んでみてください! そのご利益、その雰囲気はきっと、あなたに新たな活力を与えてくれるはずですよ!
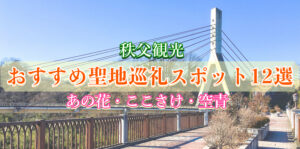
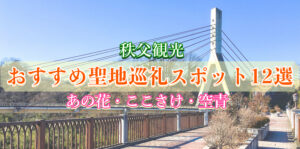
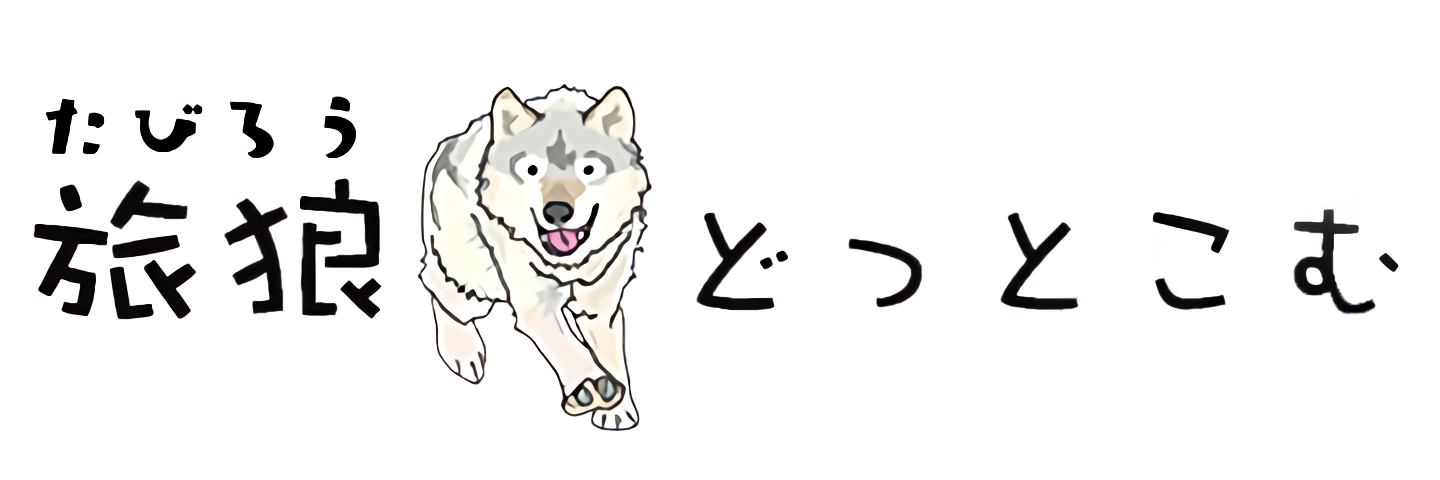


この記事へのコメントはこちらから!
コメント一覧 (2件)
[…] 👉 三峯神社についてさらに詳しくみてみる […]
[…] 👉 三峯神社について詳しく知りたい方はコチラがオススメ! […]